エキゾチック動物 EXOTIC ANIMALS
近年ではエキゾチック動物を家族に迎え入れる方も増えてきました。エキゾチックアニマルは直訳すると“風変わりな動物”ですが、簡単に言うと犬猫以外のペットのことを指します。例えばウサギやフェレット、ハムスター、チンチラやカメやカエル、セキセイインコや文鳥などの幅広い動物がこれに分類されます。
当院では、エキゾチック動物の診療にも力を入れています。飼い主様がまずは生態をよく理解し、飼育環境や運動などに気を配ることが、病気の予防につながります。
院長は犬や猫と同様のクオリティの医療をできる限り提供できるよう多くの専門的な経験を積んでいますので、いつもと様子が違うと感じた時は、早めにご来院ください。
セカンドオピニオンも積極的に受け入れております。
また、お迎えしたばかりの動物さんの健康診断や飼育の相談にも応じていますので、お気軽にご来院ください。
特殊動物に関しては診察可能かどうか事前にご連絡ください。

ウサギ
ウサギは、見た目の愛らしさ、人懐っこさ、トイレのしつけができるなどの点で比較的飼育しやすく人気の高いエキゾチック動物といえます。体調不良を隠す性質があるため、飼い主様がよく観察してあげることが大切です。

よくある病気と治療法
歯の伸びすぎ、不正咬合 ウサギの歯は自然と伸びていくものです。ペレットや葉野菜ばかり与えていると歯が削れずに伸び、噛み合わせが悪くなってしまいます。食欲が落ちた、よだれが増えたという場合には、歯のトラブルかもしれません。歯を削る処置もできますが、日頃からの食事を見直すことが重症です。
胃腸うっ滞 ストレスや季節の変わり目、換毛期など様々な原因によって、胃腸の動きが悪くなった状態のことを言います。食欲がない、便が出ていない、うずくまって動かないなど、異変を感じたらすぐに受診しましょう。急変することがあります。
子宮疾患 3~4歳以上の未避妊の女の子ウサギは50%以上が子宮腺癌や子宮内膜過形成などの何らかの子宮疾患に罹ると言われています。症状は血尿が一般的ですが、命に関わることも多いです。
早期の避妊手術で予防ができるため、当院では6カ月齢~1歳くらいでの避妊手術を推奨しています。
フェレット
感情豊かで人懐っこく、飼育する方が増えているエキゾチック動物です。病気になりやすいという一面もあるため、しっかりとケアをしてあげる必要があります。ワクチン接種やフィラリア予防も推奨しています。

よくある病気と治療法
ミミダニ症 フェレットの耳にはしばしばミミダニが寄生することがあり、特にショップからお迎えしたばかりの若い子で発症することが多いです。症状は、黒茶色の耳垢が特徴的で、痒みを伴うこともあります。駆虫薬を用いて治療します。
副腎疾患 生命維持に必要な様々なホルモンを分泌する副腎ですが、副腎腫瘍や副腎過形成になると、ホルモン分泌量が過剰になり、脱毛や攻撃性の増加、排尿困難など様々な症状を引き起こします。治療には外科的に副腎を摘出する方法と、注射によりホルモン分泌量を抑える治療があります。
インスリノーマ 加齢とともに増えてくる疾患で、低血糖を頻繁に起こします。寝ている時間が長い、意識が悪い、よだれを垂らすなどの症状があれば、低血糖に陥っている可能性があります。副腎腫瘍が原因のことも多いです。内服治療や食餌療法を行います。
ハムスター
寿命は短めですが、愛らしい仕草が魅力的で人気があります。比較的おとなしく、集合住宅でも飼育しやすいです。

よくある病気と治療法
細菌性腸炎 様々な細菌感染や、不適切な抗生物質の使用によって発症します。水様性の下痢によってお尻が濡れることから、ウェットテールと表現されます。
皮膚炎 ハムスターは皮膚炎を起こしやすいです。脱毛、皮膚をよく掻いているなど皮膚の症状が見られたら、受診してください。細菌性、アレルギー性、ダニなど原因はさまざで、それぞれに合った内服治療や環境調整を行います。
モルモット
モルモットは人に慣れやすく温厚な性格の子が多いです。平均寿命は5~6年ほどで、短毛や長毛、縮れ毛など、様々な種類がいます。

よくある病気と治療法
皮膚糸状菌症 痒みフケ、脱毛といった症状を引き起こします。若いモルモットで多く見られ、もともと家に来る前から糸状菌が体についていて、何らかのタイミングで発症することが多いです。細菌感染やダニの感染を併発することもあるため注意が必要です。
卵巣嚢胞 メスのモルモットによく見られる病気で、卵巣からのホルモン分泌量が過剰になり脱毛を引き起こしたり、大きくなった嚢胞により消化管が圧迫され食欲不振になったりします。
ハリネズミ
臆病な性格の子が多いですが、愛嬌のあるお顔が特徴的です。診察時には丸まってしまうことも多いですが、鎮静をかけることで、血液検査やレントゲン検査、エコー検査などをおこなうことができます。

よくある病気と治療法
疥癬症 もともとヒゼンダニというダニが寄生していることも多く、発症すると痒みやフケ、針が抜けるといった症状が出ます。治療には駆虫薬を使用しますが、複数回の投与が必要です。
口腔内腫瘍 3歳を超えたあたりから口が痛そう、よだれが多いといった症状がある子は口腔内腫瘍の可能性があります。検査には鎮静が必要なことが多いです。
デグー
ペットとしての歴史は比較的浅く、まだまだ診れる病院も少ないです。寿命は6,7年ほどで、とても賢い動物であり芸を覚えてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
不正咬合 デグーは前歯も奥歯も伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。何らかの原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。
消化管内ガス過剰貯留 胃腸の動きが悪くなったり、不正咬合などの原因でガスを空気を過剰に取り込んでしまうことによって起こります。食欲不振や腹痛といった症状がでます。
チンチラ
好奇心がとても旺盛で、興味があることには積極的に近づいてきます。慣れてくると飼い主さんに乗ってきたりもします。どや顔でするテヤンデイポーズがたまらないです。

よくある病気と治療法
皮膚糸状菌症 真菌をもともと持っている子も多く、顔周りや手足、背中が脱毛やフケを引き起こします。治療には抗真菌薬の長期投与が必要になります。
不正咬合 チンチラの歯は伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。外傷や不適切な食事などが原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。
フクロモモンガ
大きな目と小柄な体格が愛らしいです。また、ストレス緩和のため多頭飼育も推奨されています。

よくある病気と治療法
自咬症 フクロモモンガは精神的な問題から身体の一部をなめることが多く、次第になめ壊したり噛んでしまったりすることがあります。結果として感染が起こったり、場所によっては尿がうまく出せなくなったり命に関わることもあります。
陰茎脱 陰茎が出たまま戻らなくなってしまうことを陰茎脱といいます。早めの対処であれば陰茎を戻すことができる可能性がありますが、自咬してしまった場合や腫れてしまった場合には陰茎の切除を行うことがあります。
ジリス
好奇心旺盛で警戒心はありますが、リラックスしているときの気の抜けた姿がかわいいです。

よくある病気と治療法
不正咬合 ジリスはハムスターと同じく切歯のみ伸び続ける歯を持っています。金網ケージなどをかじることによって歯の根元に刺激が加わると正常に伸びなくなってしまい不正咬合を起こします。
皮膚疾患 ジリスに起こる皮膚疾患として、皮膚感染症や自咬症、腫瘍などがあります。
ラット
ファンシーラットがペットとして人気です。温厚な性格の子が多く、人に懐いてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
皮膚炎 細菌感染や真菌感染、寄生虫感染によって皮膚炎を起こすことがあります。また、床材のアレルギーによって皮膚の痒みがでることもあります。
呼吸器疾患 ラットはくしゃみや咳、苦しそうなど、呼吸器のトラブルが多いです。原因はとしてはウイルスや細菌の感染が多いです。
鳥類
種類によっては人によく懐き、おしゃべりをすることもあり、とても魅力的な動物です。しっかりと健康管理をしてあげると、比較的長く一緒に過ごすことができます。家にお迎えをし、慣れた頃に病院での健康診断をお勧めします。

よくある病気と治療法
卵詰まり 初産、過剰産卵、日光浴不足などの場合に発生しやすくなります。うずくまって羽を膨らませ、食欲がないといった状態であれば、すぐに受診してください。卵詰まりが長時間に及んでしまうと、ショックを起こして突然死のリスクがあります。
ビタミンB1欠乏症(いわゆる脚気) 栄養が必要な巣立ちの時期(生後1か月ごろ)に発症しやすいです。アワ玉のみで飼育していると、ビタミンB1が不足してしまいます。歩き方に異変が出たり、けいれんしたりといった症状が特徴です。ビタミンの投薬や、幼若鳥用のペレットを与えて治療します。
マクロラブダス症 胃に悪さをする真菌で、セキセイインコの20%以上が保有していると言われています。若い子や高齢な子での発症が多く、嘔吐や食欲不振を引き起こします。定期的な便検査でマクロラブダスがいないかを確認することが大切です。
爬虫類
トカゲ、ヘビ、カメといった爬虫類も、根強い人気があります。エキゾチック動物の中でも飼育は比較的手がかかります。飼育環境やエサのアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

トカゲ(ヒョウモントカゲモドキ)によくある病気と治療法
脱皮不全 うまく脱皮が進まない状態です。脱皮不全の状態が長く続くと、血流が悪化したり炎症を起こしたりするため、手助けしてあげる必要があります。爬虫類全般に生じますが、ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)はとくに多いです。脱皮中のストレス、湿度不足、カルシウムやビタミンD不足などが原因となります。
皮下膿瘍 皮膚の下に膿が溜まった状態です。低温環境などでは免疫力が低下し、わずかな傷からも細菌が入り込んで皮下膿瘍となる場合があります。抗菌薬を使った治療や、手術が選択肢となります。コブやしこりのようなものを見つけたら、皮下膿瘍の可能性があるため受診をおすすめします。
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
水カビ病 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。
転覆病(ぷかぷか病) 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。
餌の与えすぎ 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。
ウサギ
ウサギは、見た目の愛らしさ、人懐っこさ、トイレのしつけができるなどの点で比較的飼育しやすく人気の高いエキゾチック動物といえます。体調不良を隠す性質があるため、飼い主様がよく観察してあげることが大切です。

よくある病気と治療法
| 歯の伸びすぎ、不正咬合 | ウサギの歯は自然と伸びていくものです。ペレットや葉野菜ばかり与えていると歯が削れずに伸び、噛み合わせが悪くなってしまいます。食欲が落ちた、よだれが増えたという場合には、歯のトラブルかもしれません。歯を削る処置もできますが、日頃からの食事を見直すことが重症です。 |
|---|---|
| 胃腸うっ滞 | ストレスや季節の変わり目、換毛期など様々な原因によって、胃腸の動きが悪くなった状態のことを言います。食欲がない、便が出ていない、うずくまって動かないなど、異変を感じたらすぐに受診しましょう。急変することがあります。 |
| 子宮疾患 | 3~4歳以上の未避妊の女の子ウサギは50%以上が子宮腺癌や子宮内膜過形成などの何らかの子宮疾患に罹ると言われています。症状は血尿が一般的ですが、命に関わることも多いです。 |
フェレット
感情豊かで人懐っこく、飼育する方が増えているエキゾチック動物です。病気になりやすいという一面もあるため、しっかりとケアをしてあげる必要があります。ワクチン接種やフィラリア予防も推奨しています。

よくある病気と治療法
| ミミダニ症 | フェレットの耳にはしばしばミミダニが寄生することがあり、特にショップからお迎えしたばかりの若い子で発症することが多いです。症状は、黒茶色の耳垢が特徴的で、痒みを伴うこともあります。駆虫薬を用いて治療します。 |
|---|---|
| 副腎疾患 | 生命維持に必要な様々なホルモンを分泌する副腎ですが、副腎腫瘍や副腎過形成になると、ホルモン分泌量が過剰になり、脱毛や攻撃性の増加、排尿困難など様々な症状を引き起こします。治療には外科的に副腎を摘出する方法と、注射によりホルモン分泌量を抑える治療があります。 |
| インスリノーマ | 加齢とともに増えてくる疾患で、低血糖を頻繁に起こします。寝ている時間が長い、意識が悪い、よだれを垂らすなどの症状があれば、低血糖に陥っている可能性があります。副腎腫瘍が原因のことも多いです。内服治療や食餌療法を行います。 |
ハムスター
寿命は短めですが、愛らしい仕草が魅力的で人気があります。比較的おとなしく、集合住宅でも飼育しやすいです。

よくある病気と治療法
細菌性腸炎 様々な細菌感染や、不適切な抗生物質の使用によって発症します。水様性の下痢によってお尻が濡れることから、ウェットテールと表現されます。
皮膚炎 ハムスターは皮膚炎を起こしやすいです。脱毛、皮膚をよく掻いているなど皮膚の症状が見られたら、受診してください。細菌性、アレルギー性、ダニなど原因はさまざで、それぞれに合った内服治療や環境調整を行います。
モルモット
モルモットは人に慣れやすく温厚な性格の子が多いです。平均寿命は5~6年ほどで、短毛や長毛、縮れ毛など、様々な種類がいます。

よくある病気と治療法
皮膚糸状菌症 痒みフケ、脱毛といった症状を引き起こします。若いモルモットで多く見られ、もともと家に来る前から糸状菌が体についていて、何らかのタイミングで発症することが多いです。細菌感染やダニの感染を併発することもあるため注意が必要です。
卵巣嚢胞 メスのモルモットによく見られる病気で、卵巣からのホルモン分泌量が過剰になり脱毛を引き起こしたり、大きくなった嚢胞により消化管が圧迫され食欲不振になったりします。
ハリネズミ
臆病な性格の子が多いですが、愛嬌のあるお顔が特徴的です。診察時には丸まってしまうことも多いですが、鎮静をかけることで、血液検査やレントゲン検査、エコー検査などをおこなうことができます。

よくある病気と治療法
疥癬症 もともとヒゼンダニというダニが寄生していることも多く、発症すると痒みやフケ、針が抜けるといった症状が出ます。治療には駆虫薬を使用しますが、複数回の投与が必要です。
口腔内腫瘍 3歳を超えたあたりから口が痛そう、よだれが多いといった症状がある子は口腔内腫瘍の可能性があります。検査には鎮静が必要なことが多いです。
デグー
ペットとしての歴史は比較的浅く、まだまだ診れる病院も少ないです。寿命は6,7年ほどで、とても賢い動物であり芸を覚えてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
不正咬合 デグーは前歯も奥歯も伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。何らかの原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。
消化管内ガス過剰貯留 胃腸の動きが悪くなったり、不正咬合などの原因でガスを空気を過剰に取り込んでしまうことによって起こります。食欲不振や腹痛といった症状がでます。
チンチラ
好奇心がとても旺盛で、興味があることには積極的に近づいてきます。慣れてくると飼い主さんに乗ってきたりもします。どや顔でするテヤンデイポーズがたまらないです。

よくある病気と治療法
皮膚糸状菌症 真菌をもともと持っている子も多く、顔周りや手足、背中が脱毛やフケを引き起こします。治療には抗真菌薬の長期投与が必要になります。
不正咬合 チンチラの歯は伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。外傷や不適切な食事などが原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。
フクロモモンガ
大きな目と小柄な体格が愛らしいです。また、ストレス緩和のため多頭飼育も推奨されています。

よくある病気と治療法
自咬症 フクロモモンガは精神的な問題から身体の一部をなめることが多く、次第になめ壊したり噛んでしまったりすることがあります。結果として感染が起こったり、場所によっては尿がうまく出せなくなったり命に関わることもあります。
陰茎脱 陰茎が出たまま戻らなくなってしまうことを陰茎脱といいます。早めの対処であれば陰茎を戻すことができる可能性がありますが、自咬してしまった場合や腫れてしまった場合には陰茎の切除を行うことがあります。
ジリス
好奇心旺盛で警戒心はありますが、リラックスしているときの気の抜けた姿がかわいいです。

よくある病気と治療法
不正咬合 ジリスはハムスターと同じく切歯のみ伸び続ける歯を持っています。金網ケージなどをかじることによって歯の根元に刺激が加わると正常に伸びなくなってしまい不正咬合を起こします。
皮膚疾患 ジリスに起こる皮膚疾患として、皮膚感染症や自咬症、腫瘍などがあります。
ラット
ファンシーラットがペットとして人気です。温厚な性格の子が多く、人に懐いてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
皮膚炎 細菌感染や真菌感染、寄生虫感染によって皮膚炎を起こすことがあります。また、床材のアレルギーによって皮膚の痒みがでることもあります。
呼吸器疾患 ラットはくしゃみや咳、苦しそうなど、呼吸器のトラブルが多いです。原因はとしてはウイルスや細菌の感染が多いです。
鳥類
種類によっては人によく懐き、おしゃべりをすることもあり、とても魅力的な動物です。しっかりと健康管理をしてあげると、比較的長く一緒に過ごすことができます。家にお迎えをし、慣れた頃に病院での健康診断をお勧めします。

よくある病気と治療法
卵詰まり 初産、過剰産卵、日光浴不足などの場合に発生しやすくなります。うずくまって羽を膨らませ、食欲がないといった状態であれば、すぐに受診してください。卵詰まりが長時間に及んでしまうと、ショックを起こして突然死のリスクがあります。
ビタミンB1欠乏症(いわゆる脚気) 栄養が必要な巣立ちの時期(生後1か月ごろ)に発症しやすいです。アワ玉のみで飼育していると、ビタミンB1が不足してしまいます。歩き方に異変が出たり、けいれんしたりといった症状が特徴です。ビタミンの投薬や、幼若鳥用のペレットを与えて治療します。
マクロラブダス症 胃に悪さをする真菌で、セキセイインコの20%以上が保有していると言われています。若い子や高齢な子での発症が多く、嘔吐や食欲不振を引き起こします。定期的な便検査でマクロラブダスがいないかを確認することが大切です。
爬虫類
トカゲ、ヘビ、カメといった爬虫類も、根強い人気があります。エキゾチック動物の中でも飼育は比較的手がかかります。飼育環境やエサのアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

トカゲ(ヒョウモントカゲモドキ)によくある病気と治療法
脱皮不全 うまく脱皮が進まない状態です。脱皮不全の状態が長く続くと、血流が悪化したり炎症を起こしたりするため、手助けしてあげる必要があります。爬虫類全般に生じますが、ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)はとくに多いです。脱皮中のストレス、湿度不足、カルシウムやビタミンD不足などが原因となります。
皮下膿瘍 皮膚の下に膿が溜まった状態です。低温環境などでは免疫力が低下し、わずかな傷からも細菌が入り込んで皮下膿瘍となる場合があります。抗菌薬を使った治療や、手術が選択肢となります。コブやしこりのようなものを見つけたら、皮下膿瘍の可能性があるため受診をおすすめします。
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
水カビ病 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。
転覆病(ぷかぷか病) 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。
餌の与えすぎ 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。
ハムスター
寿命は短めですが、愛らしい仕草が魅力的で人気があります。比較的おとなしく、集合住宅でも飼育しやすいです。
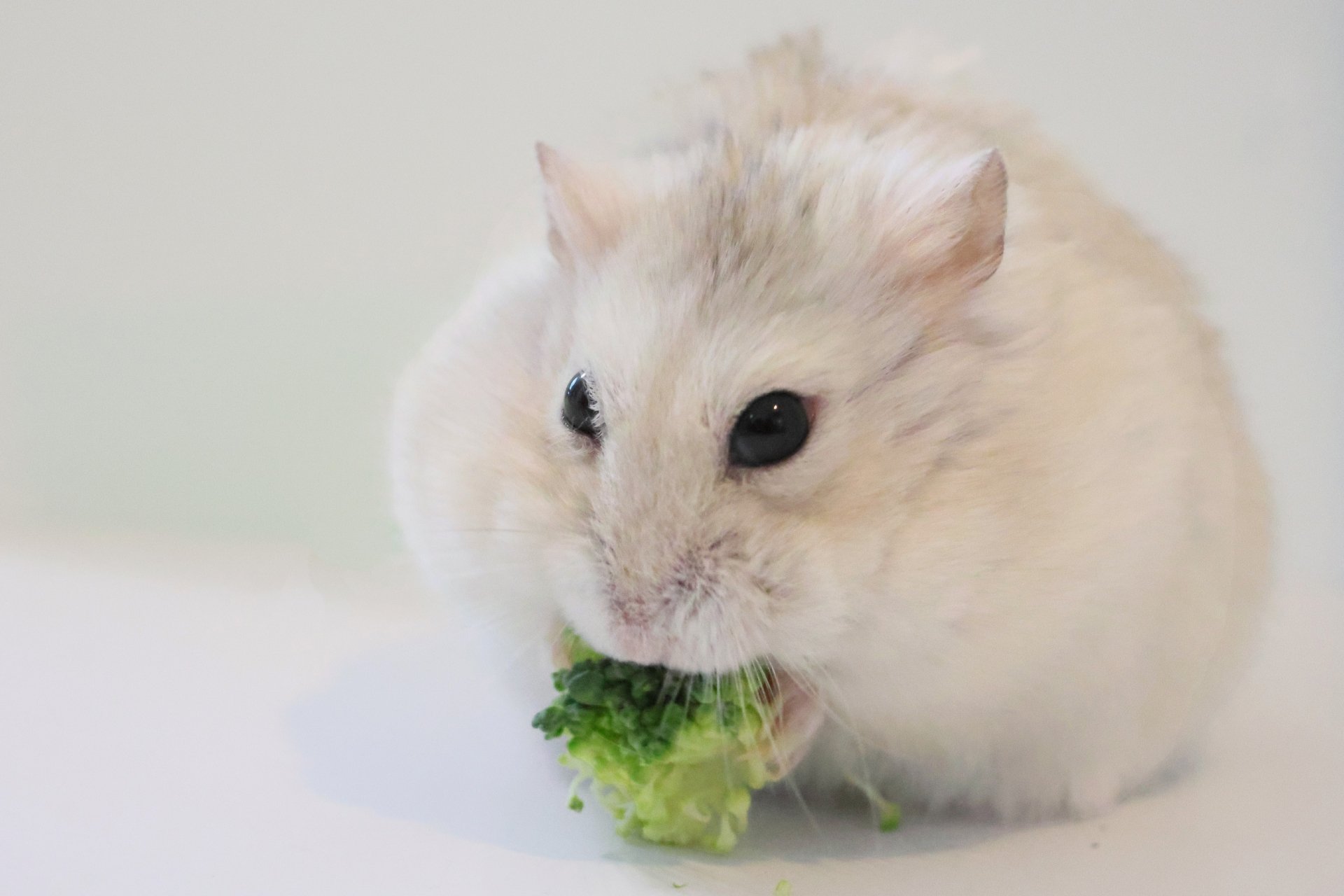
よくある病気と治療法
| 細菌性腸炎 | 様々な細菌感染や、不適切な抗生物質の使用によって発症します。水様性の下痢によってお尻が濡れることから、ウェットテールと表現されます。 |
|---|---|
| 皮膚炎 | ハムスターは皮膚炎を起こしやすいです。脱毛、皮膚をよく掻いているなど皮膚の症状が見られたら、受診してください。細菌性、アレルギー性、ダニなど原因はさまざで、それぞれに合った内服治療や環境調整を行います。 |
モルモット
モルモットは人に慣れやすく温厚な性格の子が多いです。平均寿命は5~6年ほどで、短毛や長毛、縮れ毛など、様々な種類がいます。

よくある病気と治療法
皮膚糸状菌症 痒みフケ、脱毛といった症状を引き起こします。若いモルモットで多く見られ、もともと家に来る前から糸状菌が体についていて、何らかのタイミングで発症することが多いです。細菌感染やダニの感染を併発することもあるため注意が必要です。
卵巣嚢胞 メスのモルモットによく見られる病気で、卵巣からのホルモン分泌量が過剰になり脱毛を引き起こしたり、大きくなった嚢胞により消化管が圧迫され食欲不振になったりします。
ハリネズミ
臆病な性格の子が多いですが、愛嬌のあるお顔が特徴的です。診察時には丸まってしまうことも多いですが、鎮静をかけることで、血液検査やレントゲン検査、エコー検査などをおこなうことができます。

よくある病気と治療法
疥癬症 もともとヒゼンダニというダニが寄生していることも多く、発症すると痒みやフケ、針が抜けるといった症状が出ます。治療には駆虫薬を使用しますが、複数回の投与が必要です。
口腔内腫瘍 3歳を超えたあたりから口が痛そう、よだれが多いといった症状がある子は口腔内腫瘍の可能性があります。検査には鎮静が必要なことが多いです。
デグー
ペットとしての歴史は比較的浅く、まだまだ診れる病院も少ないです。寿命は6,7年ほどで、とても賢い動物であり芸を覚えてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
不正咬合 デグーは前歯も奥歯も伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。何らかの原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。
消化管内ガス過剰貯留 胃腸の動きが悪くなったり、不正咬合などの原因でガスを空気を過剰に取り込んでしまうことによって起こります。食欲不振や腹痛といった症状がでます。
チンチラ
好奇心がとても旺盛で、興味があることには積極的に近づいてきます。慣れてくると飼い主さんに乗ってきたりもします。どや顔でするテヤンデイポーズがたまらないです。

よくある病気と治療法
皮膚糸状菌症 真菌をもともと持っている子も多く、顔周りや手足、背中が脱毛やフケを引き起こします。治療には抗真菌薬の長期投与が必要になります。
不正咬合 チンチラの歯は伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。外傷や不適切な食事などが原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。
フクロモモンガ
大きな目と小柄な体格が愛らしいです。また、ストレス緩和のため多頭飼育も推奨されています。

よくある病気と治療法
自咬症 フクロモモンガは精神的な問題から身体の一部をなめることが多く、次第になめ壊したり噛んでしまったりすることがあります。結果として感染が起こったり、場所によっては尿がうまく出せなくなったり命に関わることもあります。
陰茎脱 陰茎が出たまま戻らなくなってしまうことを陰茎脱といいます。早めの対処であれば陰茎を戻すことができる可能性がありますが、自咬してしまった場合や腫れてしまった場合には陰茎の切除を行うことがあります。
ジリス
好奇心旺盛で警戒心はありますが、リラックスしているときの気の抜けた姿がかわいいです。

よくある病気と治療法
不正咬合 ジリスはハムスターと同じく切歯のみ伸び続ける歯を持っています。金網ケージなどをかじることによって歯の根元に刺激が加わると正常に伸びなくなってしまい不正咬合を起こします。
皮膚疾患 ジリスに起こる皮膚疾患として、皮膚感染症や自咬症、腫瘍などがあります。
ラット
ファンシーラットがペットとして人気です。温厚な性格の子が多く、人に懐いてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
皮膚炎 細菌感染や真菌感染、寄生虫感染によって皮膚炎を起こすことがあります。また、床材のアレルギーによって皮膚の痒みがでることもあります。
呼吸器疾患 ラットはくしゃみや咳、苦しそうなど、呼吸器のトラブルが多いです。原因はとしてはウイルスや細菌の感染が多いです。
鳥類
種類によっては人によく懐き、おしゃべりをすることもあり、とても魅力的な動物です。しっかりと健康管理をしてあげると、比較的長く一緒に過ごすことができます。家にお迎えをし、慣れた頃に病院での健康診断をお勧めします。

よくある病気と治療法
卵詰まり 初産、過剰産卵、日光浴不足などの場合に発生しやすくなります。うずくまって羽を膨らませ、食欲がないといった状態であれば、すぐに受診してください。卵詰まりが長時間に及んでしまうと、ショックを起こして突然死のリスクがあります。
ビタミンB1欠乏症(いわゆる脚気) 栄養が必要な巣立ちの時期(生後1か月ごろ)に発症しやすいです。アワ玉のみで飼育していると、ビタミンB1が不足してしまいます。歩き方に異変が出たり、けいれんしたりといった症状が特徴です。ビタミンの投薬や、幼若鳥用のペレットを与えて治療します。
マクロラブダス症 胃に悪さをする真菌で、セキセイインコの20%以上が保有していると言われています。若い子や高齢な子での発症が多く、嘔吐や食欲不振を引き起こします。定期的な便検査でマクロラブダスがいないかを確認することが大切です。
爬虫類
トカゲ、ヘビ、カメといった爬虫類も、根強い人気があります。エキゾチック動物の中でも飼育は比較的手がかかります。飼育環境やエサのアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

トカゲ(ヒョウモントカゲモドキ)によくある病気と治療法
脱皮不全 うまく脱皮が進まない状態です。脱皮不全の状態が長く続くと、血流が悪化したり炎症を起こしたりするため、手助けしてあげる必要があります。爬虫類全般に生じますが、ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)はとくに多いです。脱皮中のストレス、湿度不足、カルシウムやビタミンD不足などが原因となります。
皮下膿瘍 皮膚の下に膿が溜まった状態です。低温環境などでは免疫力が低下し、わずかな傷からも細菌が入り込んで皮下膿瘍となる場合があります。抗菌薬を使った治療や、手術が選択肢となります。コブやしこりのようなものを見つけたら、皮下膿瘍の可能性があるため受診をおすすめします。
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
水カビ病 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。
転覆病(ぷかぷか病) 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。
餌の与えすぎ 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。
モルモット
モルモットは人に慣れやすく温厚な性格の子が多いです。平均寿命は5~6年ほどで、短毛や長毛、縮れ毛など、様々な種類がいます。

よくある病気と治療法
| 皮膚糸状菌症 | 痒みフケ、脱毛といった症状を引き起こします。若いモルモットで多く見られ、もともと家に来る前から糸状菌が体についていて、何らかのタイミングで発症することが多いです。細菌感染やダニの感染を併発することもあるため注意が必要です。 |
|---|---|
| 卵巣嚢胞 | メスのモルモットによく見られる病気で、卵巣からのホルモン分泌量が過剰になり脱毛を引き起こしたり、大きくなった嚢胞により消化管が圧迫され食欲不振になったりします。 |
ハリネズミ
臆病な性格の子が多いですが、愛嬌のあるお顔が特徴的です。診察時には丸まってしまうことも多いですが、鎮静をかけることで、血液検査やレントゲン検査、エコー検査などをおこなうことができます。

よくある病気と治療法
疥癬症 もともとヒゼンダニというダニが寄生していることも多く、発症すると痒みやフケ、針が抜けるといった症状が出ます。治療には駆虫薬を使用しますが、複数回の投与が必要です。
口腔内腫瘍 3歳を超えたあたりから口が痛そう、よだれが多いといった症状がある子は口腔内腫瘍の可能性があります。検査には鎮静が必要なことが多いです。
デグー
ペットとしての歴史は比較的浅く、まだまだ診れる病院も少ないです。寿命は6,7年ほどで、とても賢い動物であり芸を覚えてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
不正咬合 デグーは前歯も奥歯も伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。何らかの原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。
消化管内ガス過剰貯留 胃腸の動きが悪くなったり、不正咬合などの原因でガスを空気を過剰に取り込んでしまうことによって起こります。食欲不振や腹痛といった症状がでます。
チンチラ
好奇心がとても旺盛で、興味があることには積極的に近づいてきます。慣れてくると飼い主さんに乗ってきたりもします。どや顔でするテヤンデイポーズがたまらないです。

よくある病気と治療法
皮膚糸状菌症 真菌をもともと持っている子も多く、顔周りや手足、背中が脱毛やフケを引き起こします。治療には抗真菌薬の長期投与が必要になります。
不正咬合 チンチラの歯は伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。外傷や不適切な食事などが原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。
フクロモモンガ
大きな目と小柄な体格が愛らしいです。また、ストレス緩和のため多頭飼育も推奨されています。

よくある病気と治療法
自咬症 フクロモモンガは精神的な問題から身体の一部をなめることが多く、次第になめ壊したり噛んでしまったりすることがあります。結果として感染が起こったり、場所によっては尿がうまく出せなくなったり命に関わることもあります。
陰茎脱 陰茎が出たまま戻らなくなってしまうことを陰茎脱といいます。早めの対処であれば陰茎を戻すことができる可能性がありますが、自咬してしまった場合や腫れてしまった場合には陰茎の切除を行うことがあります。
ジリス
好奇心旺盛で警戒心はありますが、リラックスしているときの気の抜けた姿がかわいいです。

よくある病気と治療法
不正咬合 ジリスはハムスターと同じく切歯のみ伸び続ける歯を持っています。金網ケージなどをかじることによって歯の根元に刺激が加わると正常に伸びなくなってしまい不正咬合を起こします。
皮膚疾患 ジリスに起こる皮膚疾患として、皮膚感染症や自咬症、腫瘍などがあります。
ラット
ファンシーラットがペットとして人気です。温厚な性格の子が多く、人に懐いてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
皮膚炎 細菌感染や真菌感染、寄生虫感染によって皮膚炎を起こすことがあります。また、床材のアレルギーによって皮膚の痒みがでることもあります。
呼吸器疾患 ラットはくしゃみや咳、苦しそうなど、呼吸器のトラブルが多いです。原因はとしてはウイルスや細菌の感染が多いです。
鳥類
種類によっては人によく懐き、おしゃべりをすることもあり、とても魅力的な動物です。しっかりと健康管理をしてあげると、比較的長く一緒に過ごすことができます。家にお迎えをし、慣れた頃に病院での健康診断をお勧めします。

よくある病気と治療法
卵詰まり 初産、過剰産卵、日光浴不足などの場合に発生しやすくなります。うずくまって羽を膨らませ、食欲がないといった状態であれば、すぐに受診してください。卵詰まりが長時間に及んでしまうと、ショックを起こして突然死のリスクがあります。
ビタミンB1欠乏症(いわゆる脚気) 栄養が必要な巣立ちの時期(生後1か月ごろ)に発症しやすいです。アワ玉のみで飼育していると、ビタミンB1が不足してしまいます。歩き方に異変が出たり、けいれんしたりといった症状が特徴です。ビタミンの投薬や、幼若鳥用のペレットを与えて治療します。
マクロラブダス症 胃に悪さをする真菌で、セキセイインコの20%以上が保有していると言われています。若い子や高齢な子での発症が多く、嘔吐や食欲不振を引き起こします。定期的な便検査でマクロラブダスがいないかを確認することが大切です。
爬虫類
トカゲ、ヘビ、カメといった爬虫類も、根強い人気があります。エキゾチック動物の中でも飼育は比較的手がかかります。飼育環境やエサのアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

トカゲ(ヒョウモントカゲモドキ)によくある病気と治療法
脱皮不全 うまく脱皮が進まない状態です。脱皮不全の状態が長く続くと、血流が悪化したり炎症を起こしたりするため、手助けしてあげる必要があります。爬虫類全般に生じますが、ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)はとくに多いです。脱皮中のストレス、湿度不足、カルシウムやビタミンD不足などが原因となります。
皮下膿瘍 皮膚の下に膿が溜まった状態です。低温環境などでは免疫力が低下し、わずかな傷からも細菌が入り込んで皮下膿瘍となる場合があります。抗菌薬を使った治療や、手術が選択肢となります。コブやしこりのようなものを見つけたら、皮下膿瘍の可能性があるため受診をおすすめします。
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
水カビ病 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。
転覆病(ぷかぷか病) 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。
餌の与えすぎ 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。
ハリネズミ
臆病な性格の子が多いですが、愛嬌のあるお顔が特徴的です。診察時には丸まってしまうことも多いですが、鎮静をかけることで、血液検査やレントゲン検査、エコー検査などをおこなうことができます。

よくある病気と治療法
| 疥癬症 | もともとヒゼンダニというダニが寄生していることも多く、発症すると痒みやフケ、針が抜けるといった症状が出ます。治療には駆虫薬を使用しますが、複数回の投与が必要です。 |
|---|---|
| 口腔内腫瘍 | 3歳を超えたあたりから口が痛そう、よだれが多いといった症状がある子は口腔内腫瘍の可能性があります。検査には鎮静が必要なことが多いです。 |
デグー
ペットとしての歴史は比較的浅く、まだまだ診れる病院も少ないです。寿命は6,7年ほどで、とても賢い動物であり芸を覚えてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
不正咬合 デグーは前歯も奥歯も伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。何らかの原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。
消化管内ガス過剰貯留 胃腸の動きが悪くなったり、不正咬合などの原因でガスを空気を過剰に取り込んでしまうことによって起こります。食欲不振や腹痛といった症状がでます。
チンチラ
好奇心がとても旺盛で、興味があることには積極的に近づいてきます。慣れてくると飼い主さんに乗ってきたりもします。どや顔でするテヤンデイポーズがたまらないです。

よくある病気と治療法
皮膚糸状菌症 真菌をもともと持っている子も多く、顔周りや手足、背中が脱毛やフケを引き起こします。治療には抗真菌薬の長期投与が必要になります。
不正咬合 チンチラの歯は伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。外傷や不適切な食事などが原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。
フクロモモンガ
大きな目と小柄な体格が愛らしいです。また、ストレス緩和のため多頭飼育も推奨されています。

よくある病気と治療法
自咬症 フクロモモンガは精神的な問題から身体の一部をなめることが多く、次第になめ壊したり噛んでしまったりすることがあります。結果として感染が起こったり、場所によっては尿がうまく出せなくなったり命に関わることもあります。
陰茎脱 陰茎が出たまま戻らなくなってしまうことを陰茎脱といいます。早めの対処であれば陰茎を戻すことができる可能性がありますが、自咬してしまった場合や腫れてしまった場合には陰茎の切除を行うことがあります。
ジリス
好奇心旺盛で警戒心はありますが、リラックスしているときの気の抜けた姿がかわいいです。

よくある病気と治療法
不正咬合 ジリスはハムスターと同じく切歯のみ伸び続ける歯を持っています。金網ケージなどをかじることによって歯の根元に刺激が加わると正常に伸びなくなってしまい不正咬合を起こします。
皮膚疾患 ジリスに起こる皮膚疾患として、皮膚感染症や自咬症、腫瘍などがあります。
ラット
ファンシーラットがペットとして人気です。温厚な性格の子が多く、人に懐いてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
皮膚炎 細菌感染や真菌感染、寄生虫感染によって皮膚炎を起こすことがあります。また、床材のアレルギーによって皮膚の痒みがでることもあります。
呼吸器疾患 ラットはくしゃみや咳、苦しそうなど、呼吸器のトラブルが多いです。原因はとしてはウイルスや細菌の感染が多いです。
鳥類
種類によっては人によく懐き、おしゃべりをすることもあり、とても魅力的な動物です。しっかりと健康管理をしてあげると、比較的長く一緒に過ごすことができます。家にお迎えをし、慣れた頃に病院での健康診断をお勧めします。

よくある病気と治療法
卵詰まり 初産、過剰産卵、日光浴不足などの場合に発生しやすくなります。うずくまって羽を膨らませ、食欲がないといった状態であれば、すぐに受診してください。卵詰まりが長時間に及んでしまうと、ショックを起こして突然死のリスクがあります。
ビタミンB1欠乏症(いわゆる脚気) 栄養が必要な巣立ちの時期(生後1か月ごろ)に発症しやすいです。アワ玉のみで飼育していると、ビタミンB1が不足してしまいます。歩き方に異変が出たり、けいれんしたりといった症状が特徴です。ビタミンの投薬や、幼若鳥用のペレットを与えて治療します。
マクロラブダス症 胃に悪さをする真菌で、セキセイインコの20%以上が保有していると言われています。若い子や高齢な子での発症が多く、嘔吐や食欲不振を引き起こします。定期的な便検査でマクロラブダスがいないかを確認することが大切です。
爬虫類
トカゲ、ヘビ、カメといった爬虫類も、根強い人気があります。エキゾチック動物の中でも飼育は比較的手がかかります。飼育環境やエサのアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

トカゲ(ヒョウモントカゲモドキ)によくある病気と治療法
脱皮不全 うまく脱皮が進まない状態です。脱皮不全の状態が長く続くと、血流が悪化したり炎症を起こしたりするため、手助けしてあげる必要があります。爬虫類全般に生じますが、ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)はとくに多いです。脱皮中のストレス、湿度不足、カルシウムやビタミンD不足などが原因となります。
皮下膿瘍 皮膚の下に膿が溜まった状態です。低温環境などでは免疫力が低下し、わずかな傷からも細菌が入り込んで皮下膿瘍となる場合があります。抗菌薬を使った治療や、手術が選択肢となります。コブやしこりのようなものを見つけたら、皮下膿瘍の可能性があるため受診をおすすめします。
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
水カビ病 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。
転覆病(ぷかぷか病) 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。
餌の与えすぎ 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。
デグー
ペットとしての歴史は比較的浅く、まだまだ診れる病院も少ないです。寿命は6,7年ほどで、とても賢い動物であり芸を覚えてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
| 不正咬合 | デグーは前歯も奥歯も伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。何らかの原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。 |
|---|---|
| 消化管内ガス過剰貯留 | 胃腸の動きが悪くなったり、不正咬合などの原因でガスを空気を過剰に取り込んでしまうことによって起こります。食欲不振や腹痛といった症状がでます。 |
チンチラ
好奇心がとても旺盛で、興味があることには積極的に近づいてきます。慣れてくると飼い主さんに乗ってきたりもします。どや顔でするテヤンデイポーズがたまらないです。

よくある病気と治療法
皮膚糸状菌症 真菌をもともと持っている子も多く、顔周りや手足、背中が脱毛やフケを引き起こします。治療には抗真菌薬の長期投与が必要になります。
不正咬合 チンチラの歯は伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。外傷や不適切な食事などが原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。
フクロモモンガ
大きな目と小柄な体格が愛らしいです。また、ストレス緩和のため多頭飼育も推奨されています。

よくある病気と治療法
自咬症 フクロモモンガは精神的な問題から身体の一部をなめることが多く、次第になめ壊したり噛んでしまったりすることがあります。結果として感染が起こったり、場所によっては尿がうまく出せなくなったり命に関わることもあります。
陰茎脱 陰茎が出たまま戻らなくなってしまうことを陰茎脱といいます。早めの対処であれば陰茎を戻すことができる可能性がありますが、自咬してしまった場合や腫れてしまった場合には陰茎の切除を行うことがあります。
ジリス
好奇心旺盛で警戒心はありますが、リラックスしているときの気の抜けた姿がかわいいです。

よくある病気と治療法
不正咬合 ジリスはハムスターと同じく切歯のみ伸び続ける歯を持っています。金網ケージなどをかじることによって歯の根元に刺激が加わると正常に伸びなくなってしまい不正咬合を起こします。
皮膚疾患 ジリスに起こる皮膚疾患として、皮膚感染症や自咬症、腫瘍などがあります。
ラット
ファンシーラットがペットとして人気です。温厚な性格の子が多く、人に懐いてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
皮膚炎 細菌感染や真菌感染、寄生虫感染によって皮膚炎を起こすことがあります。また、床材のアレルギーによって皮膚の痒みがでることもあります。
呼吸器疾患 ラットはくしゃみや咳、苦しそうなど、呼吸器のトラブルが多いです。原因はとしてはウイルスや細菌の感染が多いです。
鳥類
種類によっては人によく懐き、おしゃべりをすることもあり、とても魅力的な動物です。しっかりと健康管理をしてあげると、比較的長く一緒に過ごすことができます。家にお迎えをし、慣れた頃に病院での健康診断をお勧めします。

よくある病気と治療法
卵詰まり 初産、過剰産卵、日光浴不足などの場合に発生しやすくなります。うずくまって羽を膨らませ、食欲がないといった状態であれば、すぐに受診してください。卵詰まりが長時間に及んでしまうと、ショックを起こして突然死のリスクがあります。
ビタミンB1欠乏症(いわゆる脚気) 栄養が必要な巣立ちの時期(生後1か月ごろ)に発症しやすいです。アワ玉のみで飼育していると、ビタミンB1が不足してしまいます。歩き方に異変が出たり、けいれんしたりといった症状が特徴です。ビタミンの投薬や、幼若鳥用のペレットを与えて治療します。
マクロラブダス症 胃に悪さをする真菌で、セキセイインコの20%以上が保有していると言われています。若い子や高齢な子での発症が多く、嘔吐や食欲不振を引き起こします。定期的な便検査でマクロラブダスがいないかを確認することが大切です。
爬虫類
トカゲ、ヘビ、カメといった爬虫類も、根強い人気があります。エキゾチック動物の中でも飼育は比較的手がかかります。飼育環境やエサのアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

トカゲ(ヒョウモントカゲモドキ)によくある病気と治療法
脱皮不全 うまく脱皮が進まない状態です。脱皮不全の状態が長く続くと、血流が悪化したり炎症を起こしたりするため、手助けしてあげる必要があります。爬虫類全般に生じますが、ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)はとくに多いです。脱皮中のストレス、湿度不足、カルシウムやビタミンD不足などが原因となります。
皮下膿瘍 皮膚の下に膿が溜まった状態です。低温環境などでは免疫力が低下し、わずかな傷からも細菌が入り込んで皮下膿瘍となる場合があります。抗菌薬を使った治療や、手術が選択肢となります。コブやしこりのようなものを見つけたら、皮下膿瘍の可能性があるため受診をおすすめします。
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
水カビ病 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。
転覆病(ぷかぷか病) 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。
餌の与えすぎ 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。
チンチラ
好奇心がとても旺盛で、興味があることには積極的に近づいてきます。慣れてくると飼い主さんに乗ってきたりもします。どや顔でするテヤンデイポーズがたまらないです。

よくある病気と治療法
| 皮膚糸状菌症 | 真菌をもともと持っている子も多く、顔周りや手足、背中が脱毛やフケを引き起こします。治療には抗真菌薬の長期投与が必要になります。 |
|---|---|
| 不正咬合 | チンチラの歯は伸び続けることが特徴ですが、牧草をしっかり噛むことで削れていきます。外傷や不適切な食事などが原因で歯が伸びてしまうことで不正咬合を発症し、食欲不振やよだれなどの症状を引き起こします。 |
フクロモモンガ
大きな目と小柄な体格が愛らしいです。また、ストレス緩和のため多頭飼育も推奨されています。

よくある病気と治療法
自咬症 フクロモモンガは精神的な問題から身体の一部をなめることが多く、次第になめ壊したり噛んでしまったりすることがあります。結果として感染が起こったり、場所によっては尿がうまく出せなくなったり命に関わることもあります。
陰茎脱 陰茎が出たまま戻らなくなってしまうことを陰茎脱といいます。早めの対処であれば陰茎を戻すことができる可能性がありますが、自咬してしまった場合や腫れてしまった場合には陰茎の切除を行うことがあります。
ジリス
好奇心旺盛で警戒心はありますが、リラックスしているときの気の抜けた姿がかわいいです。

よくある病気と治療法
不正咬合 ジリスはハムスターと同じく切歯のみ伸び続ける歯を持っています。金網ケージなどをかじることによって歯の根元に刺激が加わると正常に伸びなくなってしまい不正咬合を起こします。
皮膚疾患 ジリスに起こる皮膚疾患として、皮膚感染症や自咬症、腫瘍などがあります。
ラット
ファンシーラットがペットとして人気です。温厚な性格の子が多く、人に懐いてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
皮膚炎 細菌感染や真菌感染、寄生虫感染によって皮膚炎を起こすことがあります。また、床材のアレルギーによって皮膚の痒みがでることもあります。
呼吸器疾患 ラットはくしゃみや咳、苦しそうなど、呼吸器のトラブルが多いです。原因はとしてはウイルスや細菌の感染が多いです。
鳥類
種類によっては人によく懐き、おしゃべりをすることもあり、とても魅力的な動物です。しっかりと健康管理をしてあげると、比較的長く一緒に過ごすことができます。家にお迎えをし、慣れた頃に病院での健康診断をお勧めします。

よくある病気と治療法
卵詰まり 初産、過剰産卵、日光浴不足などの場合に発生しやすくなります。うずくまって羽を膨らませ、食欲がないといった状態であれば、すぐに受診してください。卵詰まりが長時間に及んでしまうと、ショックを起こして突然死のリスクがあります。
ビタミンB1欠乏症(いわゆる脚気) 栄養が必要な巣立ちの時期(生後1か月ごろ)に発症しやすいです。アワ玉のみで飼育していると、ビタミンB1が不足してしまいます。歩き方に異変が出たり、けいれんしたりといった症状が特徴です。ビタミンの投薬や、幼若鳥用のペレットを与えて治療します。
マクロラブダス症 胃に悪さをする真菌で、セキセイインコの20%以上が保有していると言われています。若い子や高齢な子での発症が多く、嘔吐や食欲不振を引き起こします。定期的な便検査でマクロラブダスがいないかを確認することが大切です。
爬虫類
トカゲ、ヘビ、カメといった爬虫類も、根強い人気があります。エキゾチック動物の中でも飼育は比較的手がかかります。飼育環境やエサのアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

トカゲ(ヒョウモントカゲモドキ)によくある病気と治療法
脱皮不全 うまく脱皮が進まない状態です。脱皮不全の状態が長く続くと、血流が悪化したり炎症を起こしたりするため、手助けしてあげる必要があります。爬虫類全般に生じますが、ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)はとくに多いです。脱皮中のストレス、湿度不足、カルシウムやビタミンD不足などが原因となります。
皮下膿瘍 皮膚の下に膿が溜まった状態です。低温環境などでは免疫力が低下し、わずかな傷からも細菌が入り込んで皮下膿瘍となる場合があります。抗菌薬を使った治療や、手術が選択肢となります。コブやしこりのようなものを見つけたら、皮下膿瘍の可能性があるため受診をおすすめします。
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
水カビ病 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。
転覆病(ぷかぷか病) 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。
餌の与えすぎ 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。
フクロモモンガ
大きな目と小柄な体格が愛らしいです。また、ストレス緩和のため多頭飼育も推奨されています。

よくある病気と治療法
| 自咬症 | フクロモモンガは精神的な問題から身体の一部をなめることが多く、次第になめ壊したり噛んでしまったりすることがあります。結果として感染が起こったり、場所によっては尿がうまく出せなくなったり命に関わることもあります。 |
|---|---|
| 陰茎脱 | 陰茎が出たまま戻らなくなってしまうことを陰茎脱といいます。早めの対処であれば陰茎を戻すことができる可能性がありますが、自咬してしまった場合や腫れてしまった場合には陰茎の切除を行うことがあります。 |
ジリス
好奇心旺盛で警戒心はありますが、リラックスしているときの気の抜けた姿がかわいいです。

よくある病気と治療法
不正咬合 ジリスはハムスターと同じく切歯のみ伸び続ける歯を持っています。金網ケージなどをかじることによって歯の根元に刺激が加わると正常に伸びなくなってしまい不正咬合を起こします。
皮膚疾患 ジリスに起こる皮膚疾患として、皮膚感染症や自咬症、腫瘍などがあります。
ラット
ファンシーラットがペットとして人気です。温厚な性格の子が多く、人に懐いてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
皮膚炎 細菌感染や真菌感染、寄生虫感染によって皮膚炎を起こすことがあります。また、床材のアレルギーによって皮膚の痒みがでることもあります。
呼吸器疾患 ラットはくしゃみや咳、苦しそうなど、呼吸器のトラブルが多いです。原因はとしてはウイルスや細菌の感染が多いです。
鳥類
種類によっては人によく懐き、おしゃべりをすることもあり、とても魅力的な動物です。しっかりと健康管理をしてあげると、比較的長く一緒に過ごすことができます。家にお迎えをし、慣れた頃に病院での健康診断をお勧めします。

よくある病気と治療法
卵詰まり 初産、過剰産卵、日光浴不足などの場合に発生しやすくなります。うずくまって羽を膨らませ、食欲がないといった状態であれば、すぐに受診してください。卵詰まりが長時間に及んでしまうと、ショックを起こして突然死のリスクがあります。
ビタミンB1欠乏症(いわゆる脚気) 栄養が必要な巣立ちの時期(生後1か月ごろ)に発症しやすいです。アワ玉のみで飼育していると、ビタミンB1が不足してしまいます。歩き方に異変が出たり、けいれんしたりといった症状が特徴です。ビタミンの投薬や、幼若鳥用のペレットを与えて治療します。
マクロラブダス症 胃に悪さをする真菌で、セキセイインコの20%以上が保有していると言われています。若い子や高齢な子での発症が多く、嘔吐や食欲不振を引き起こします。定期的な便検査でマクロラブダスがいないかを確認することが大切です。
爬虫類
トカゲ、ヘビ、カメといった爬虫類も、根強い人気があります。エキゾチック動物の中でも飼育は比較的手がかかります。飼育環境やエサのアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

トカゲ(ヒョウモントカゲモドキ)によくある病気と治療法
脱皮不全 うまく脱皮が進まない状態です。脱皮不全の状態が長く続くと、血流が悪化したり炎症を起こしたりするため、手助けしてあげる必要があります。爬虫類全般に生じますが、ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)はとくに多いです。脱皮中のストレス、湿度不足、カルシウムやビタミンD不足などが原因となります。
皮下膿瘍 皮膚の下に膿が溜まった状態です。低温環境などでは免疫力が低下し、わずかな傷からも細菌が入り込んで皮下膿瘍となる場合があります。抗菌薬を使った治療や、手術が選択肢となります。コブやしこりのようなものを見つけたら、皮下膿瘍の可能性があるため受診をおすすめします。
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
水カビ病 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。
転覆病(ぷかぷか病) 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。
餌の与えすぎ 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。
ジリス
好奇心旺盛で警戒心はありますが、リラックスしているときの気の抜けた姿がかわいいです。

よくある病気と治療法
| 不正咬合 | ジリスはハムスターと同じく切歯のみ伸び続ける歯を持っています。金網ケージなどをかじることによって歯の根元に刺激が加わると正常に伸びなくなってしまい不正咬合を起こします。 |
|---|---|
| 皮膚疾患 | ジリスに起こる皮膚疾患として、皮膚感染症や自咬症、腫瘍などがあります。 |
ラット
ファンシーラットがペットとして人気です。温厚な性格の子が多く、人に懐いてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
皮膚炎 細菌感染や真菌感染、寄生虫感染によって皮膚炎を起こすことがあります。また、床材のアレルギーによって皮膚の痒みがでることもあります。
呼吸器疾患 ラットはくしゃみや咳、苦しそうなど、呼吸器のトラブルが多いです。原因はとしてはウイルスや細菌の感染が多いです。
鳥類
種類によっては人によく懐き、おしゃべりをすることもあり、とても魅力的な動物です。しっかりと健康管理をしてあげると、比較的長く一緒に過ごすことができます。家にお迎えをし、慣れた頃に病院での健康診断をお勧めします。

よくある病気と治療法
卵詰まり 初産、過剰産卵、日光浴不足などの場合に発生しやすくなります。うずくまって羽を膨らませ、食欲がないといった状態であれば、すぐに受診してください。卵詰まりが長時間に及んでしまうと、ショックを起こして突然死のリスクがあります。
ビタミンB1欠乏症(いわゆる脚気) 栄養が必要な巣立ちの時期(生後1か月ごろ)に発症しやすいです。アワ玉のみで飼育していると、ビタミンB1が不足してしまいます。歩き方に異変が出たり、けいれんしたりといった症状が特徴です。ビタミンの投薬や、幼若鳥用のペレットを与えて治療します。
マクロラブダス症 胃に悪さをする真菌で、セキセイインコの20%以上が保有していると言われています。若い子や高齢な子での発症が多く、嘔吐や食欲不振を引き起こします。定期的な便検査でマクロラブダスがいないかを確認することが大切です。
爬虫類
トカゲ、ヘビ、カメといった爬虫類も、根強い人気があります。エキゾチック動物の中でも飼育は比較的手がかかります。飼育環境やエサのアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

トカゲ(ヒョウモントカゲモドキ)によくある病気と治療法
脱皮不全 うまく脱皮が進まない状態です。脱皮不全の状態が長く続くと、血流が悪化したり炎症を起こしたりするため、手助けしてあげる必要があります。爬虫類全般に生じますが、ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)はとくに多いです。脱皮中のストレス、湿度不足、カルシウムやビタミンD不足などが原因となります。
皮下膿瘍 皮膚の下に膿が溜まった状態です。低温環境などでは免疫力が低下し、わずかな傷からも細菌が入り込んで皮下膿瘍となる場合があります。抗菌薬を使った治療や、手術が選択肢となります。コブやしこりのようなものを見つけたら、皮下膿瘍の可能性があるため受診をおすすめします。
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
水カビ病 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。
転覆病(ぷかぷか病) 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。
餌の与えすぎ 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。
ラット
ファンシーラットがペットとして人気です。温厚な性格の子が多く、人に懐いてくれる子もいます。

よくある病気と治療法
| 皮膚炎 | 細菌感染や真菌感染、寄生虫感染によって皮膚炎を起こすことがあります。また、床材のアレルギーによって皮膚の痒みがでることもあります。 |
|---|---|
| 呼吸器疾患 | ラットはくしゃみや咳、苦しそうなど、呼吸器のトラブルが多いです。原因はとしてはウイルスや細菌の感染が多いです。 |
鳥類
種類によっては人によく懐き、おしゃべりをすることもあり、とても魅力的な動物です。しっかりと健康管理をしてあげると、比較的長く一緒に過ごすことができます。家にお迎えをし、慣れた頃に病院での健康診断をお勧めします。

よくある病気と治療法
卵詰まり 初産、過剰産卵、日光浴不足などの場合に発生しやすくなります。うずくまって羽を膨らませ、食欲がないといった状態であれば、すぐに受診してください。卵詰まりが長時間に及んでしまうと、ショックを起こして突然死のリスクがあります。
ビタミンB1欠乏症(いわゆる脚気) 栄養が必要な巣立ちの時期(生後1か月ごろ)に発症しやすいです。アワ玉のみで飼育していると、ビタミンB1が不足してしまいます。歩き方に異変が出たり、けいれんしたりといった症状が特徴です。ビタミンの投薬や、幼若鳥用のペレットを与えて治療します。
マクロラブダス症 胃に悪さをする真菌で、セキセイインコの20%以上が保有していると言われています。若い子や高齢な子での発症が多く、嘔吐や食欲不振を引き起こします。定期的な便検査でマクロラブダスがいないかを確認することが大切です。
爬虫類
トカゲ、ヘビ、カメといった爬虫類も、根強い人気があります。エキゾチック動物の中でも飼育は比較的手がかかります。飼育環境やエサのアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

トカゲ(ヒョウモントカゲモドキ)によくある病気と治療法
脱皮不全 うまく脱皮が進まない状態です。脱皮不全の状態が長く続くと、血流が悪化したり炎症を起こしたりするため、手助けしてあげる必要があります。爬虫類全般に生じますが、ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)はとくに多いです。脱皮中のストレス、湿度不足、カルシウムやビタミンD不足などが原因となります。
皮下膿瘍 皮膚の下に膿が溜まった状態です。低温環境などでは免疫力が低下し、わずかな傷からも細菌が入り込んで皮下膿瘍となる場合があります。抗菌薬を使った治療や、手術が選択肢となります。コブやしこりのようなものを見つけたら、皮下膿瘍の可能性があるため受診をおすすめします。
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
水カビ病 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。
転覆病(ぷかぷか病) 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。
餌の与えすぎ 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。
鳥類
種類によっては人によく懐き、おしゃべりをすることもあり、とても魅力的な動物です。しっかりと健康管理をしてあげると、比較的長く一緒に過ごすことができます。家にお迎えをし、慣れた頃に病院での健康診断をお勧めします。

よくある病気と治療法
| 卵詰まり | 初産、過剰産卵、日光浴不足などの場合に発生しやすくなります。うずくまって羽を膨らませ、食欲がないといった状態であれば、すぐに受診してください。卵詰まりが長時間に及んでしまうと、ショックを起こして突然死のリスクがあります。 |
|---|---|
| ビタミンB1欠乏症(いわゆる脚気) | 栄養が必要な巣立ちの時期(生後1か月ごろ)に発症しやすいです。アワ玉のみで飼育していると、ビタミンB1が不足してしまいます。歩き方に異変が出たり、けいれんしたりといった症状が特徴です。ビタミンの投薬や、幼若鳥用のペレットを与えて治療します。 |
| マクロラブダス症 | 胃に悪さをする真菌で、セキセイインコの20%以上が保有していると言われています。若い子や高齢な子での発症が多く、嘔吐や食欲不振を引き起こします。定期的な便検査でマクロラブダスがいないかを確認することが大切です。 |
爬虫類
トカゲ、ヘビ、カメといった爬虫類も、根強い人気があります。エキゾチック動物の中でも飼育は比較的手がかかります。飼育環境やエサのアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

トカゲ(ヒョウモントカゲモドキ)によくある病気と治療法
脱皮不全 うまく脱皮が進まない状態です。脱皮不全の状態が長く続くと、血流が悪化したり炎症を起こしたりするため、手助けしてあげる必要があります。爬虫類全般に生じますが、ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)はとくに多いです。脱皮中のストレス、湿度不足、カルシウムやビタミンD不足などが原因となります。
皮下膿瘍 皮膚の下に膿が溜まった状態です。低温環境などでは免疫力が低下し、わずかな傷からも細菌が入り込んで皮下膿瘍となる場合があります。抗菌薬を使った治療や、手術が選択肢となります。コブやしこりのようなものを見つけたら、皮下膿瘍の可能性があるため受診をおすすめします。
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
水カビ病 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。
転覆病(ぷかぷか病) 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。
餌の与えすぎ 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。
爬虫類
トカゲ、ヘビ、カメといった爬虫類も、根強い人気があります。エキゾチック動物の中でも飼育は比較的手がかかります。飼育環境やエサのアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

トカゲ(ヒョウモントカゲモドキ)によくある病気と治療法
| 脱皮不全 | うまく脱皮が進まない状態です。脱皮不全の状態が長く続くと、血流が悪化したり炎症を起こしたりするため、手助けしてあげる必要があります。爬虫類全般に生じますが、ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)はとくに多いです。脱皮中のストレス、湿度不足、カルシウムやビタミンD不足などが原因となります。 |
|---|---|
| 皮下膿瘍 | 皮膚の下に膿が溜まった状態です。低温環境などでは免疫力が低下し、わずかな傷からも細菌が入り込んで皮下膿瘍となる場合があります。抗菌薬を使った治療や、手術が選択肢となります。コブやしこりのようなものを見つけたら、皮下膿瘍の可能性があるため受診をおすすめします。 |
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
水カビ病 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。
転覆病(ぷかぷか病) 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。
餌の与えすぎ 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。
両生類
幼生と変態後で見た目も生活の仕方も大きく変わるのが、両生類を飼育する魅力の1つです。その分、しっかりと生態を理解してお世話してあげることが欠かせません。院長もウーパールーパーを飼育しています。

ウーパールーパーによくある病気と治療法
| 水カビ病 | 白っぽい綿のようなものが体の表面についていたら、水カビ病を疑います。水質の悪化があるかもしれませんので、水を換え、水温の調整で回復を待ちます。薬浴が有効な場合もありますが、ウーパールーパーの皮膚はとても敏感なので、慎重に実施しなければなりません。 |
|---|---|
| 転覆病(ぷかぷか病) | 不適切な環境や食事、感染症などが原因で身体にガスがたまり、水面に浮いてしまう病気です。環境や食事を整える、ガスを抜く、抗生物質の投与などで治療しますが、完治は難しい場合もあります。 |
| 餌の与えすぎ | 餌を与えすぎると、消化不良や内臓脂肪の蓄積が原因で死んでしまうことがあります。体の大きさにもよりますが、毎日餌を与える必要はありません。 |


