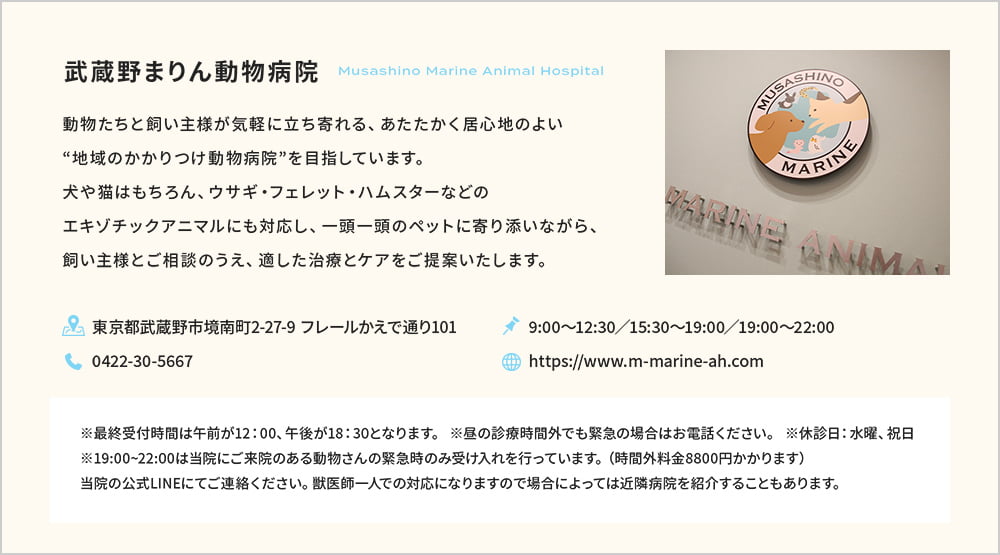カエルの風船病 〜原因・症状・治療について〜
〜原因・症状・治療について〜
1.はじめに
カエルを飼育していると、体がパンパンに膨らんでいる、浮いて泳げないといった異常を見かけることがあるかもしれません。
体がまるで風船のように膨らむため風船病と呼ばれますが獣医学では浮腫症候群という名前がつけられています。体内に異常に空気やガスがたまる病気で、放置すると命に関わることもあります。
本記事では、風船病の原因や症状、治療方法について獣医師の視点からわかりやすくご説明します。
2.風船病とは?
風船病とは、カエルの皮下や体腔内に空気や水分が異常にたまる状態を指します。その結果、体がふくらみ、通常の姿勢が取れなくなったり泳げなくなります。水生種・陸生種問わずさまざまな種類のカエルで発生します。原因はいくつかあると考えられており腎疾患、皮膚病、循環不全などが挙げられます。
両生類は浸透性に優れた皮膚を持ち、皮膚や膀胱からも水分吸収を行うことができます。吸収された水分は腎臓で濃縮され尿として排出されますがカエルは体内の窒素代謝物やイオンなどを排泄するために多くの水を必要とするからです。尿は膀胱に蓄められ、一定の量で排出されますがカエルが脱水状態になった時はこの膀胱内の尿から水分を再吸収することによって水分補給を行います。腎臓の機能が低下してしまった場合水の排泄がうまくいかず必要以上に体への再吸収が促進する結果水分が体の中に溜まり続けてしまいます。
両生類の皮膚には水分吸収の役割を担っている部位があります。その部分に感染や炎症が起きると水分吸収がうまくできなくなりイオンバランスの調節にも異常をきたす場合があり、これにより浮腫が起こるとも言われています。また、この感染症が全身に広がってしまい敗血症という状態までになると腎臓を含む全身の臓器の機能が低下してしまい浮腫の原因となります。
両生類は心臓とは別にリンパ液を全身に循環させる働きをもつリンパ心臓という装置を持っています。このリンパ心臓は不適切な保定、注射、外傷、腫瘍、痛風など様々な原因により異常が起き、これにより局所的に浮腫むことがあります。
3.診断と治療
カエルの風船病について、多くは分かっていません。よく見られる症状としてはお腹が膨らんできた、元気食欲がない、などです。腹部が大きくなることによりうまく移動が行えなかったり水中でバランスが取れず転倒するなども見られます。
<診断>
外貌の観察やレントゲン検査、超音波検査を行い体腔内にガスが溜まっているのか、水分が溜まっているのかを判断します。場合によっては穿刺をして溜まっている液体の色や内容物の観察をします。
<治療>
原因の疾患を見つけ治療をすることが理想的ですができる検査が限られるため原因の特定は難しいことが多いです。
そのため対症療法として体内のバランスを整えるためにカエルさんの体液と等張の両生類リンゲルを使用し、抗生物質の投与も同時に行うこともあります。また、状態次第では塩分の濃度がやや高めのお水で塩浴を行うことがあります。この方法は浸透圧の差を利用して体から水分を排出させることを目的とした方法です。これらの方法で良くなることもありますが症状が進行していれば亡くなってしまう子も多いです。
4.まとめ
原因は細菌感染や内臓疾患など多岐にわたりますが飼育環境が原因で体調を崩してしまうこともあります。水を清潔に保つ、温度を調節するなどの日常的な環境管理が何より大切です。
「体が膨らんでいる」「元気食欲がない」などの異変に気づいたら、動物病院に相談しましょう。
できる検査や治療が限られるカエルさんですが当院でもできる限りの対応をさせていただきます。些細なことでも気になることがあればお気軽にご相談ください。
武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の 犬・猫やウサギ・ハムスター・フェレット・モルモット・デグー・フクロモモンガ・インコ・トカゲ・カメ・カエルなどのエキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」です。 セカンドオピニオンとしても気軽にお頼りください!
地域の皆様向けに、当院におけるエキゾチックアニマル診療を解説しています。ご興味がある方はこちらも確認ください。
エキゾチックアニマル診療【武蔵野・三鷹・小金井・調布・西東京地域の皆様】