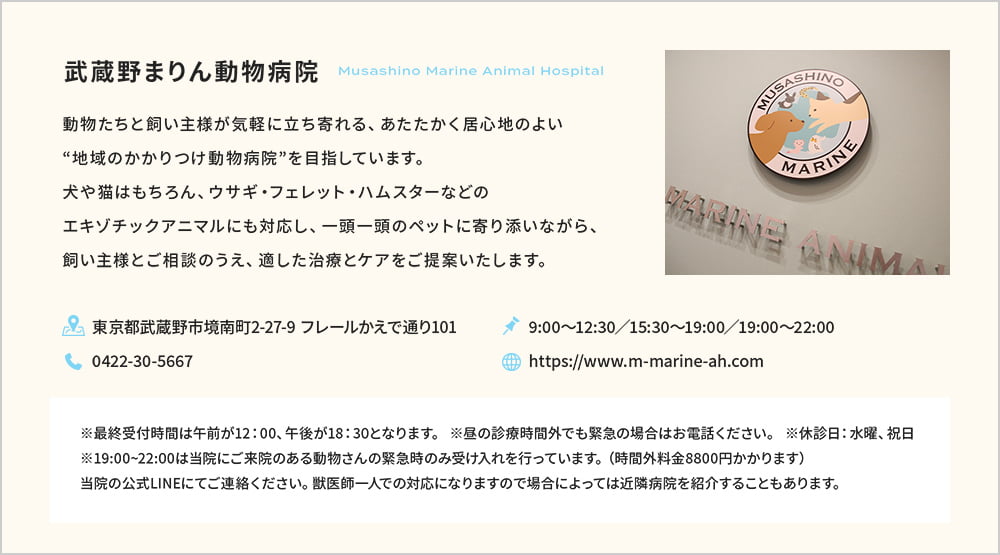犬の認知症について 〜シニア期にみられる変化とサポート方法〜
〜シニア期にみられる変化とサポート方法〜
1.はじめに
近年、獣医療の進歩やフードの品質向上により、犬の平均寿命は大きく延びています。
それに伴い増えてきているのが「犬の認知症」で獣医学では認知機能不全症候群という名前が付けられています。
高齢の犬が夜鳴きをしたり、ぐるぐると同じ場所を歩き回るなどの行動が見られた場合、実は脳の老化が進行しているサインかもしれません。
犬の認知症は早期に気づき、生活環境を整えることで飼い主さんとの生活の質を保つことができます。
今回は、獣医師の視点から犬の認知症について詳しく解説します。
2.犬の認知症とは?
犬の認知症とは、明確には定義されていませんが脳の老化によって記憶力や学習能力、認識力、睡眠リズムなどが低下する状態を指します。
人のアルツハイマー病と似た変化が脳内で起こると考えられていましたが現在は否定され、詳しい病態は未だ分かっていません。
3.主な症状
犬の認知症の症状は、行動や生活リズムの変化として現れ、6つのカテゴリーに分けられています。
◯見当識障害
家の中で迷う
壁に向かって立ち止まる
◯社会的交流の変化
飼い主に無関心になる
◯睡眠サイクルの変化
夜間に活動的になる
夜鳴きをする
◯学習した行動の変化
トイレの失敗が増える
おすわりなどの指示が分からなくなる
◯活動の変化
ウロウロと歩き回る
活動性の減少
◯不安
不安行動の増加
これらの症状が徐々に進行していくのが特徴で、症状が見られる犬の脳内では様々な加齢性の病理変化が認められることが分かっていますが特徴的な変化などや病態は未だ解明されていません。
4.診断と治療
<診断>
犬の認知症は血液検査や画像検査で明確にこの数値だから認知症といった診断を行うことは出来ません。
そのため、考えられる他の疾患を除外しつつ以下のような方法で総合的に診断します。
問診・身体検査:飼い主さんから普段の様子を詳しく聞き取ります。診察室内での状態も観察します。
血液検査・画像検査:必要に応じて甲状腺疾患や内臓疾患など、似た症状を起こす病気を除外するための検査を行います。
MRI検査:脳腫瘍や脳炎など他の脳疾患を確認するために行うこともあります。
<治療・管理>
現時点で認知症を完全に治す薬はありませんがサプリメントや食事療法で進行を緩やかにさせ、生活の質を保つことを目標に環境の整備をします。
◯環境面のケア
角や隙間で行き詰まる場合には円形サークルなどで生活空間を囲い、怪我のリスクを減らします。リラックスできる場所や水飲み場、トイレなどを行きやすい場所に揃え場所をコロコロと変えないこともポイントです。
ふらつき、転倒などがある場合は足に着用する滑り止め防止グッズを使用したり床に敷物を敷くなどで対策ができます。
適度なお散歩や遊びも刺激になるので無理の無い範囲で継続しましょう。
◯サプリメント
抗酸化物質であるビタミン群や認知機能改善が期待されるDHAやEPAなどの栄養素が良いとされています。
◯食事療法
先述の栄養素が含まれる高齢犬用のご飯を選択することも1つです。
ただし、疾患や肥満など他に身体的問題がある場合はそれにあった療法食が優先されるので動物病院で相談してください。
◯補助的薬物療法
夜間の不眠、不安、興奮などはそれぞれの症状に対してのお薬で緩和出来る場合があります。
5.まとめ
犬の認知症は、現在のところ根本的治療法はありませんが早めに気づき、環境や生活を整えることで進行を緩やかに出来る可能性があります。
体内時計を維持するためにできるだけ毎日同じ時間に食事やお散歩をしたり、遊びや簡単なしつけをすることも脳の刺激になります。
飼い主様もわんちゃんも無理のない範囲でケアを行うことが大切です。
当院でもシニア犬の認知症ケアの相談を承っており、サプリメント等のご紹介も可能です。些細なことでもお気軽にご相談ください。
武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の 犬・猫やウサギ・ハムスター・フェレット・モルモット・デグー・フクロモモンガ・インコ・トカゲ・カメ・カエルなどのエキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」です。 セカンドオピニオンとしても気軽にお頼りください!