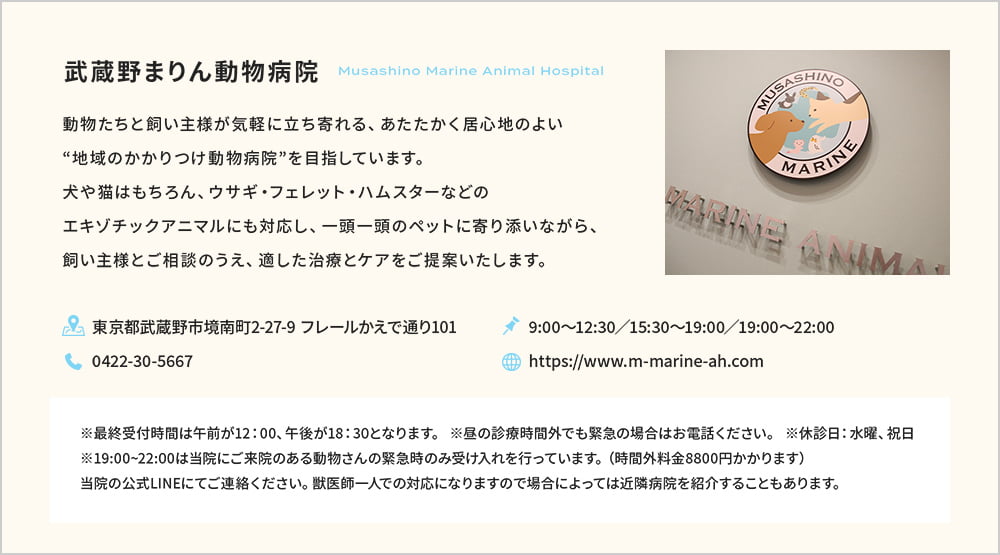子猫の社会化期について〜性格をつくる大切な時間〜
1.はじめに
猫ちゃんにも「人懐っこい子」「少し怖がりな子」など、性格の違いがあります。 その性格や行動の基盤は、実は子猫の社会化期に大きな影響を受けています。
社会化期とは、「外の世界に慣れるための大切な学習期間」のことです。この時期にどんな体験をしたかが、その子猫の一生を左右するといっても過言ではありません。
今回は、獣医師の視点から「子猫の社会化期」について解説します。
2.子猫の社会化期とは?
社会化期とは、子猫が人や環境に順応する力を身につける発達段階のことで、子猫の社会化期は生後2週齢〜9週齢ごろと言われています。
この時期に出会った人や音、におい、生活環境は「怖くないもの」として脳に刻まれやすく、将来の性格に直結します。
例えば、
社会化がうまくいった子 → 人懐っこく、知らない環境でも落ち着いて過ごせる
社会化が不足した子 → 人見知りや怖がりが強く、問題行動につながりやすい
というように、違いが現れやすくなります。
生まれてすぐの社会化期にはまず親や兄弟と接して猫同士のコミュニケーション方法を学びます。その後新しい飼い主さんのもとで様々な経験を通して人とのコミュニケーション方法を学びます。
3.社会化期に経験させたいこと
社会化期にどんなことを学ばせるかが、将来の安心した生活につながります。以下のような経験を少しずつ、無理のない範囲で取り入れてあげましょう。
① 人との触れ合い
例)
家族以外の人(大人・子ども・男女)と接する
やさしく撫でてもらう
獣医師や看護師など「お世話をしてくれる人」との関わり
→ 多様な人と良い体験をすることで、人懐っこく落ち着いた子に育ちやすくなります。
② 音や環境に慣れる
例)
掃除機やドライヤーなどの生活音
テレビやラジオの音
外の車の音や雷の音
→小さい頃から「怖くない」と学んでおくことで、成猫になってからのストレスを減らせます。
② 猫や他の動物との関わり
例)
兄弟猫や母猫との遊び方や接し方
同居の動物さんとの交流
→ 兄弟猫や母猫と過ごすことで、噛む力の加減や遊び方を学びます。 早すぎる時期に母猫から離されると、社会性が十分に育たず、攻撃的・臆病になりやすいと言われています。現在、出生後56日を超えていない子猫の販売は法律で禁止されています。これは早くに母猫と引き離される悪影響が大きいからです。そのため社会化期を過ぎていることがほとんどですがお家に迎え入れた時点からで遅くないので色々な経験をさせるように意識しましょう。同居の動物さんがいる場合はワクチン接種が済んだら少しずつ交流させましょう。

4.子猫の社会化で注意するポイント
・無理をさせない
・抱っこを嫌がるときは短時間でやめる
・大きな音をいきなり聞かせない
「怖かった記憶」がついてしまうと逆効果になるので、ポジティブな経験にすることが大切です。
また、社会化期はワクチン接種が完了していないことも多く、外の猫や環境に触れると感染症のリスクがあります。外出させるのではなく、家庭内での出来事を中心に経験させましょう。「人と一緒にいると安心できる」と学ばせることで、成猫になってからも人と良い関係を築きやすくなります。
5.まとめ
子猫の社会化期は、生後2週齢〜9週齢という短い時間です。この時期にどんな体験をするかで、将来の性格や人との関わり方が大きく変わります。
・人に慣れる(抱っこ、触られる練習)
・音や環境に慣れる
・ポジティブな経験を積み重ねる
これらを意識することで、人懐っこく安心して暮らせる成猫へと育っていきます。
逆に、この時期に経験が不足すると、攻撃的になったり怖がりな子になってしまうのでできるだけ多くの経験を積ませてあげることが理想です。お家に迎え入れた時点からのトレーニングでも遅くないので少しずつ行っていきましょう。
子猫をお迎えした飼い主様に知っていただきたいブログをまとめました。合わせてご参照ください!
→【男の子の猫ちゃんをお迎えする飼い主様へ】 猫の去勢手術は必要?メリット・注意点・時期をわかりやすく解説!
→【女の子の猫ちゃんをお迎えする飼い主様へ】 猫の避妊手術は必要?メリット・注意点・時期をわかりやすく解説!
→【猫ちゃんの健康を守るために】 ワクチンは毎年必要?種類・スケジュール・注意点を解説
→【必読】ノミ・マダニ予防はなぜ必要?愛犬・愛猫を守るために知っておきたいこと
当院でもご相談を受け付けています。些細なことでもお気軽にいらっしゃってください。
武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の 犬・猫やウサギ・ハムスター・フェレット・モルモット・デグー・フクロモモンガ・インコ・トカゲ・カメ・カエルなどのエキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」です。 セカンドオピニオンとしても気軽にお頼りください!