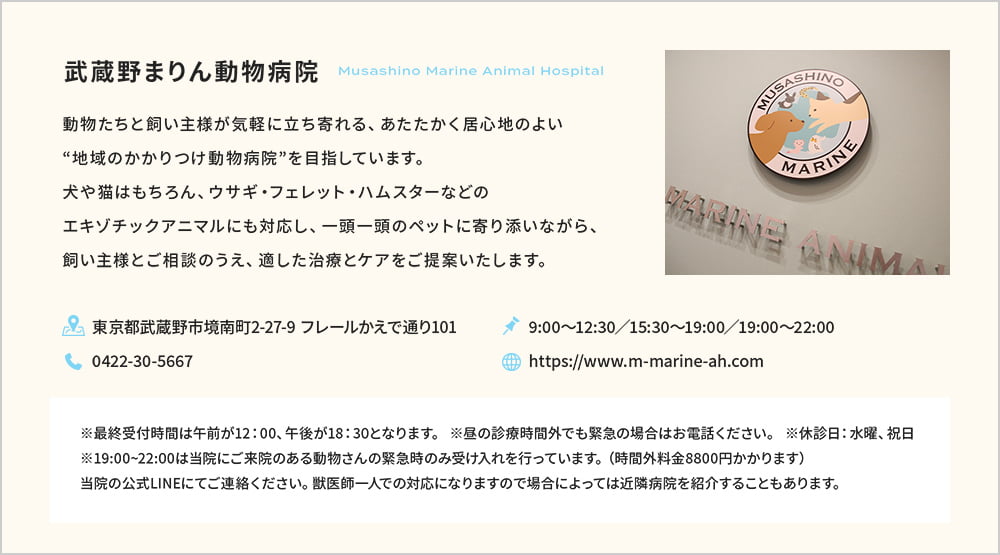フクロモモンガの自咬症とは?〜原因・症状・治療まで〜
1.はじめに
フクロモモンガは、その大きな瞳と滑空する姿が魅力的で、近年ペットとして飼育する方が増えています。しかし、犬や猫に比べるとまだ研究や情報が少なく、特有の病気や行動に戸惑う飼い主さんも少なくありません。その中でも注意すべき病気のひとつが 自咬症(じこうしょう) です。
これは文字通り、自分の体を咬んでしまう病気で、進行すると命に関わることもある深刻な問題です。今回は、フクロモモンガの自咬症について、原因・症状・治療の流れを獣医師がわかりやすく解説します。
2.自咬症とは?
自咬症とは、フクロモモンガが自分の体を執拗に咬んで傷つけてしまう状態を指します。
多くは生殖器や尾、手足、臭腺(胸のあたり)などを狙うことが多く、出血や感染を伴うケースもあります。放置すると傷が悪化して膿んだり、壊死してしまうこともあり、最悪の場合は命に関わることもあります。
犬や猫の「舐性皮膚炎」に似ていますが、フクロモモンガの場合は咬む力が強く、短期間で重症化しやすいのが特徴です。
3.原因
自咬症の原因はひとつではなく、ストレス・病気・環境要因が複雑に絡み合って起こると考えられています。
フクロモモンガは群れで暮らす社会性の高い動物です。単独飼育で寂しさが強くなると自咬につながることがあります。また、引っ越し、新しいペットの導入、大きな音、ケージの場所の移動など環境の変化などもストレスの要因となります。ケージが狭い、遊ぶ時間が少ないなどから運動不足になることもあります。カルシウム不足やビタミン不足が体調不良やイライラにつながることがあります。
自咬症を引き起こす主な部位は臭腺や陰部などでその部分の炎症や分泌異常などに伴うことがあります。痛みや痒みなどの違和感から咬むようになることも考えられるため何らかの原因による炎症や傷も二次的な自咬症の原因となる場合があります。特にオスでは分泌物が溜まることによる陰茎脱も多く、これにより自咬症が引き起こされることもあります。
4.主な症状
自咬症の初期には些細なサインが出ます。飼い主さんが早く気づくことが非常に大切です。
・毛が薄くなっている部分がある
・同じ場所をしきりに舐めたり噛んだりする
・出血やかさぶたがある
・尻尾や生殖器に赤みや腫れがある
・落ち着きがなくジージーと鳴くことが増える
・食欲が落ちる、活動量が減る
悪化すると大きな傷や感染、膿の排出が見られ、緊急治療が必要になります。
5.診断と治療
<診断>
動物病院では、まず身体検査や問診を行い、咬んでいる部位や背景を確認します。何が原因であるかを精査することが重要なので必要に応じて、傷口の皮膚検査・血液検査・レントゲン検査・エコー検査などを実施し、感染症や外傷、腫瘤などの有無を調べます。
<治療>
治療は原因の除去と傷の処置が基本です。
外科的処置・投薬
→傷の洗浄、消毒を行います。傷口の範囲が広い場合は鎮静下で縫合処置を行う場合もあります。また処置後には抗生物質や消炎剤の処方をします。痛み止めを併用する場合もあります。オスの場合は去勢手術も有効です。
保護具の使用
→エリザベスカラーを使いさらに傷を広げることを防ぎます。
環境改善
→疾患の精査やそれに伴う治療反応から自咬症の原因となる疾患を除外した場合には環境改善を試みます。食事内容や栄養バランスの見直しをしたり、ケージを広くし、遊び場や隠れ家を増やすなどです。また、飼い主さんとのスキンシップや遊ぶ時間を増やすこともストレス軽減の方法です。
自咬症は再発しやすいため、 治療と並行して飼育環境の見直しが必須 です。
6.まとめ
フクロモモンガの自咬症は、飼い主さんにとってショッキングな症状ですが、決して珍しいものではありません。
原因はストレスや病気などさまざまで、一度始まると急速に悪化することもあります。
毎日スキンシップをとり孤独感を軽減させてあげましょう。多頭飼育も自咬症の予防になります。
早期発見・早期対応で、フクロモモンガの生活の質を大きく守ることができます。
「少し毛が薄いかな?」「同じ場所を気にしているな」と感じたら、早めに動物病院に相談してください。
地域の皆様向けに、当院におけるエキゾチックアニマル診療を解説しています。ご興味がある方はこちらも確認ください。
エキゾチックアニマル診療【武蔵野・三鷹・小金井・調布・西東京地域の皆様】
武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の 犬・猫やウサギ・ハムスター・フェレット・モルモット・デグー・フクロモモンガ・インコ・トカゲ・カメ・カエルなどのエキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」です。 セカンドオピニオンとしても気軽にお頼りください。