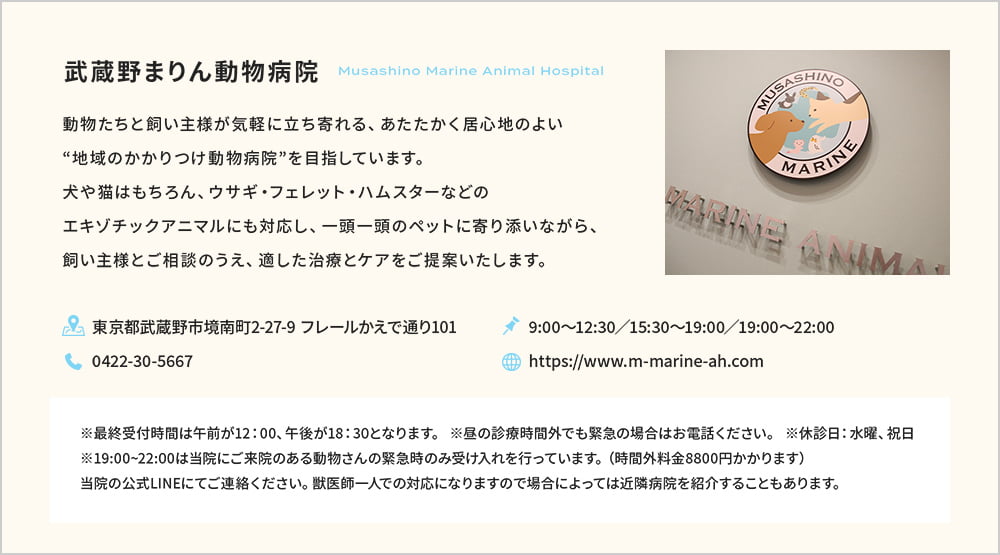【犬】水をよく飲む、おしっこが多いのは病気のサイン?考えられる原因と治療法
考えられる原因と治療法
目次
1.はじめに
「最近、水を飲む量が増えたかも」
「おしっこの回数が今までより増えた」
こうした変化は飼い主さんが日常で気づきやすい症状の一つです。
しかし、そのまま見過ごしてしまうと実は病気のサインだったということも少なくありません。
この記事では犬の「多飲多尿」について考えられる原因、注意すべき症状、病院での検査や治療内容についてご説明します。

2.「多飲多尿」とは?どこからが異常なの?
〇多飲とは?
一般的に1日の飲水量が体重1Kgあたり100mlを超える状態を「多飲」と定義します。
例えば、5Kgの犬の場合、1日500ml以上の水を飲んでいれば多飲と考えられます。
ちなみに健康な犬の飲水量の目安は1日50~60ml/Kgと言われています。
〇多尿とは?
尿の量が明らかに増えたり、排尿の回数が増える状態を示します。
多飲と同時に現れることが多いですがどちらか片方だけでも注意が必要です。
〇こんな行動が見られたら要注意
・水を飲んでもすぐにまた飲む
・夜中に水を飲むために何度も起きる
・おしっこの回数が増えた、色が薄い
・飲水量を量ると明らかに増えている
日常のちょっとした変化こそが体の異変のサインです。
3.なぜ多飲多尿になるの?仕組みを簡単に解説
水分摂取と尿排泄は体の水分バランスを保つ重要な機能です。
腎臓・ホルモン・脳・膀胱などが連携してバランスを保っています。
多飲多尿が起きる背景には次のような仕組みの乱れが関与しています。
・腎臓で尿がうまく濃縮できない(薄い尿が大量に出る)
・ホルモン分泌の異常で水の調節が効かなくなる。
・血糖値が高くなり尿中に糖が出ると過剰に水分が排出される。
・感染や腫瘍などによって異常な利尿反応が起きている。
このように尿として体の水分が多く排泄されるようになるとそれを補うためにたくさんお水を飲むようになります。このことから多飲多尿の背景には内臓疾患が隠れていることが多いのです。
4.多飲多尿がよくみられる病気
高齢犬にしばしばみられる病気で腎臓の機能が徐々に低下していきます。
腎臓が尿を濃くできなくなり薄く大量の尿がでるようになります。
<症状>
・食欲低下・体重減少
・脱水
・多飲多尿
<治療>
食事療法(腎臓療法食)・点滴・薬物療法
インスリンというホルモンの不足により血糖値が異常に高くなる病気です。
尿中に糖が出ることで体の水分が一緒に排泄され、多飲多尿が起こります。
<症状>
・食欲はあるが体重が減る
・多飲多尿
・元気がない、嘔吐(進行時)
<治療>
インスリン注射、血糖コントロール、食事管理
副腎という臓器から過剰にホルモン(コルチゾール)が分泌される病気。
多飲多尿の代表的な原因の一つです。
<症状>
・お腹がぽっこり膨らむ
・毛が薄くなる、皮膚がかさかさする
・食欲が増える
・多飲多尿
<治療>
基本的にホルモン抑制薬の内服
子宮内に膿が溜まる感染症で命に関わることもある危険な病気です。
細菌が出す毒素により多飲多尿の症状が出ることがあります。
<症状>
・陰部から膿や血が出る
・お腹が張っている
・食欲不振、元気がない
・多飲多尿
<治療>
基本的に手術(子宮・卵巣摘出)を行います。
子宮蓄膿症について詳しく説明したブログはこちらです。
→子宮蓄膿症ってどんな病気?~避妊していない女の子に起こる、命に関わる病気とは~
5.動物病院での検査と治療
多飲多尿が疑われる場合、動物病院では身体検査に加え以下のような検査を行います。
〇血液検査
腎臓・肝臓・血糖値・電解質などをチェック
〇尿検査
尿の濃さ、糖、タンパク、潜血、細菌の有無などの確認
〇レントゲン検査・超音波検査
腎臓や副腎、膀胱、子宮などの構造的異常を調べる
〇ホルモン検査
クッシング症候群などの診断に使用。
6.飼い主さんができること・受診時のポイント
できるだけ早期に病気を見つけるために日頃から以下のことを意識しましょう。
・飲水量に変化が無いかチェックする
・尿の色や量、回数の変化に注意する
・元気食欲、体型の変化に注意する
・可能なら尿を採取して病院へ持参する
7.まとめ
多飲多尿は加齢や環境の変化だけでなく重大な病気のサインであることが多い症状です。「いつもと違う」と感じたときは自己判断せず早めに動物病院を受診してください。
早期発見・早期治療介入が大切です。
何か気になることがあればお気軽にご相談ください!
武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の
犬・猫・エキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」