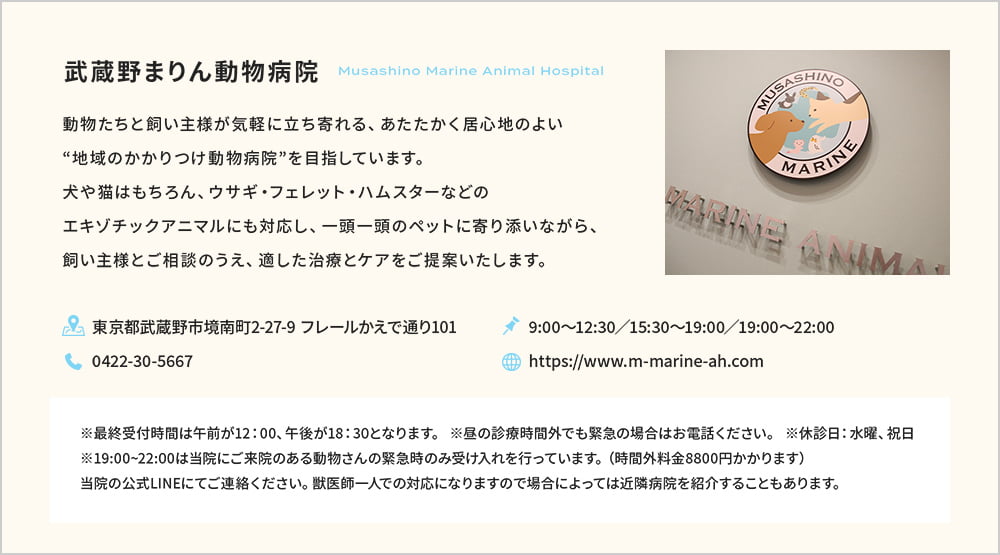トカゲの代謝性骨疾患~治療や予防法について~
はじめに
近年、その飼いやすさからヒョウモントカゲモドキを筆頭にトカゲの飼育頭数が増えていると思われます(正確にはヒョウモントカゲモドキはヤモリですが)。そしてトカゲを飼われている方の中で、代謝性骨疾患(クル病)という言葉を聞いたことがある方も少なくないかもしれません。この病気は予防が大切ではありますが、まだまだ浸透していないことも多いため、今回はそんな代謝性骨疾患に関して獣医師が解説します。
1.代謝性骨疾患とは
トカゲが食事によって摂取したカルシウムは、体内にあるビタミンD3が活性化することにより腸管から吸収されますが、昼行性のトカゲ(フトアゴヒゲトカゲなど)と夜行性のトカゲ(ヒョウモントカゲモドキなど)では考え方が少し異なります。
昼行性のトカゲ
紫外線を浴びることでビタミンD3の活性が高まります。そのため、食事中のカルシウムと、適切な紫外線ライトが大切です。
夜行性のトカゲ
基本的には紫外線がなくても体内のビタミンD3は活性化されます。そのため、食事中の十分な量のカルシウムが大切です。
ただし、一般的な昆虫食ではカルシウムが不足してしまうため、昆虫食の場合にはダスティング(昆虫にカルシウムを添加すること)が必要になります。人工餌を食べている場合には、基本的にカルシウムがしっかりと含まれているため添加の必要はありません。
また、食事中にビタミンD3を添加することに関しては意見が分かれていますが、過剰になることは良くないため、添加するとしても週に1回ほどが好ましいと思われます。
以上のようにして血液中のカルシウム濃度は維持されますが、何らかの要因で血液中のカルシウムが少なくなってしまうと、骨からカルシウムを放出して血液中に送らなければならなくなり、結果として骨は脆弱化してしまい、様々な症状を引き起こしてします。
このような、低カルシウムに起因して症状を起こすことが一般的に代謝性骨疾患と呼ばれています。
2.症状
基本的には骨の異常ですが、代謝性骨疾患が持続することで低カルシウム血症も併発することがあります。
骨の異常
背骨・尾骨・下顎骨の変形、発育不良など
低カルシウム血症
食欲不振、活動性の低下、震え、けいれんなど
3.検査・診断
検査は主にX線検査と血液検査になります。
X線検査
骨折の有無や、骨密度、骨の変形などを確認します。
血液検査
主に血中のカルシウムの濃度を確認します。
ただし、どちらの検査もはじめのうちは異常とならないこともあるため、症状や飼育環境など、総合的に評価して診断します。
4.治療
現在の症状によって、カルシウム、ビタミンD3、痛み止めの注射や経口摂取を行っていきます。
また、後述する栄養管理と環境の見直しも同時に行っていきます。具体的には、昼行性のトカゲでは紫外線ライトを適切に使用する、昆虫食を主食とする場合にはダスティングを行うなどです。
ただし、一度骨変形などを起こしてしまうとそれを治すことは難しいため、早期の治療介入が大切です。
5.予防
適切な栄養管理と環境の整備が大切です。
栄養管理
食事により適度なカルシウムを与えることが重要です。人工餌を与えるか、昆虫食であればダスティングを行うことが必要です。
環境の整備
昼行性のトカゲでは適切な紫外線ライトを使用することが重要です。ものにもよりますが、基本的には6カ月ごとに交換することを推奨しています。
また、紫外線ライトでなく日光浴をしているのであれば、窓越しではガラスに吸収されてしまうため注意が必要です。
まとめ
トカゲの代謝性骨疾患は、飼育者の知識が増えてきたことや人工餌の普及により以前よりは少なくなりましたが、まだまだ診る機会の多い病気です。複合的な要因が隠れていることが多いため完全とは言えませんが、適切な予防によって防げることが多いです。また、早期であれば症状を軽減させることや治すことができる可能性もあるため、気になる症状があれば早めに獣医師に相談しましょう。
♦地域の皆様向けに、当院におけるエキゾチックアニマル診療を解説しています。ご興味がある方はこちらも確認ください。
エキゾチックアニマル診療【武蔵野・三鷹・小金井・調布・西東京地域の皆様】
武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の
犬・猫・エキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」