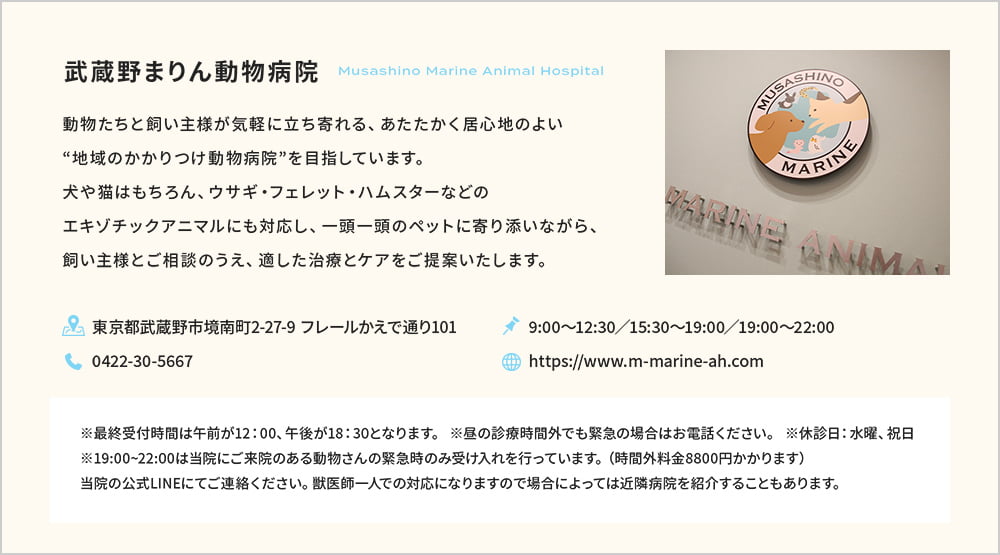猫の糖尿病~症状・診断・治療について~
1.はじめに
猫の糖尿病は、中高齢の猫に見られる内分泌(ホルモン)の病気です。 名前だけ聞くと「人間の病気」というイメージがあるかもしれませんが、実は猫も糖尿病になります。 糖尿病は放置すると命に関わる合併症を引き起こす可能性がありますが、正しい知識と日常の管理によって、長く元気に暮らすことができます。 この記事では、猫の糖尿病について飼い主さん向けにわかりやすく解説します。
2.糖尿病ってどんな病気?
糖尿病は、血液の中の糖(血糖値)が高い状態が続く病気です。 主な原因は、「インスリン」というホルモンの量が足りないか、働きが悪くなることです。
インスリンは膵臓(すいぞう)から分泌され、血液中の糖を細胞に取り込み、エネルギーとして利用できるようにします。このインスリンが不足したりうまく働かなくなると、血液中の糖が高いままになり、さまざまな症状が現れます。
糖尿病は大きく分けて「1型」と「2型」がありますが、猫の多くは人間でいう2型に似たタイプです。
膵臓にあるβ細胞という細胞が傷つき、インスリンを十分に作れなくなることから血糖値を下げられず高血糖の状態が続きます。原因としては膵炎や免疫の異常が考えられます。
インスリンは作られていても体の細胞がその働きを受け入れにくくなることがあります。これをインスリン抵抗性と呼び以下の条件で起こりやすくなります。
・肥満:特に室内飼いで運動不足の猫に多い
・加齢:10歳以上で発症しやすい
・性別:オス猫に多い傾向
・ホルモン異常:クッシング症候群や甲状腺機能亢進症など
・薬の影響:長期間のステロイド投与など
3.主な症状
糖尿病の猫では、次のような症状が見られます。
・おしっこの量が増える(多尿)、水をたくさん飲む(多飲)
・よく食べるのに痩せていく
・元気がない、毛づやが悪くなる
・後ろ足がふらつく(末期の神経障害)
・食欲がなくなり、ぐったりする(糖尿病性ケトアシドーシス)
特に「多飲・多尿・体重減少」は糖尿病の典型的なサインなので、早めの受診が必要です。
4.診断と治療
<診断>
動物病院では、身体検査に加えて以下のような検査を組み合わせて診断します。
- 血液検査:高血糖かどうか、その他臓器に異常が無いかを確認します。
- 尿検査:尿糖の有無やケトン体の有無を調べます。
- フルクトサミンまたは糖化アルブミン測定:数週間の平均的な血糖値を反映する検査で、ストレスによる一時的な高血糖との区別に有効です。
他の病気の見落としが無いようにレントゲン検査やエコー検査も行います。
<治療>
猫の糖尿病は基本的にインスリン注射と食事管理で症状が出ない状態を目指します。
→猫の糖尿病はインスリン抵抗性が多いですが次第にインスリンの分泌量も減っていることが多いのでインスリン注射で管理をします。1日2回、皮下に注射し、血糖値が適切な値になるように調節します。飼い主さんが自宅で行うことが多く、獣医師がやり方を指導します。体にセンサーを付けると採血をしなくても血糖値が測れる機械がありお家での血糖値測定に役立ちます。猫ではインスリン治療によって、一部の症例で「寛解(薬が不要になる状態)」が期待できます。
→高タンパク・低炭水化物の療法食が推奨されます。肥満体型の子は少しずつダイエットを意識しながら治療を行います。
他にも病院で定期的に身体検査を行ったり血糖値をモニタリングしながら必要に応じてインスリンの投与量を調節します。近年では新たな治療の選択肢として経口薬も発売されました。

5.合併症
糖尿病が進行したりうまくコントロールが出来ていないと以下のような危険な状態を引き起こします。
・糖尿病性ケトアシドーシス(命に関わる緊急状態)
・低血糖(インスリン過剰時)
・神経障害
・感染症(尿路感染症など)
・高浸透圧高血圧症候群(重度の高血糖と脱水状態)
動物病院での緊急対応や入院管理が必要なこともあるので早めに受診しましょう。
6.まとめ
猫の糖尿病は、早期発見と継続的な治療が何より大切な病気です。 「水をたくさん飲む」「尿の量が増えた」「痩せてきた」などの変化は見逃さず、すぐに動物病院に相談しましょう。 定期的な健康診断もおすすめしています。当院でも実施可能なのでお気軽にご相談ください。