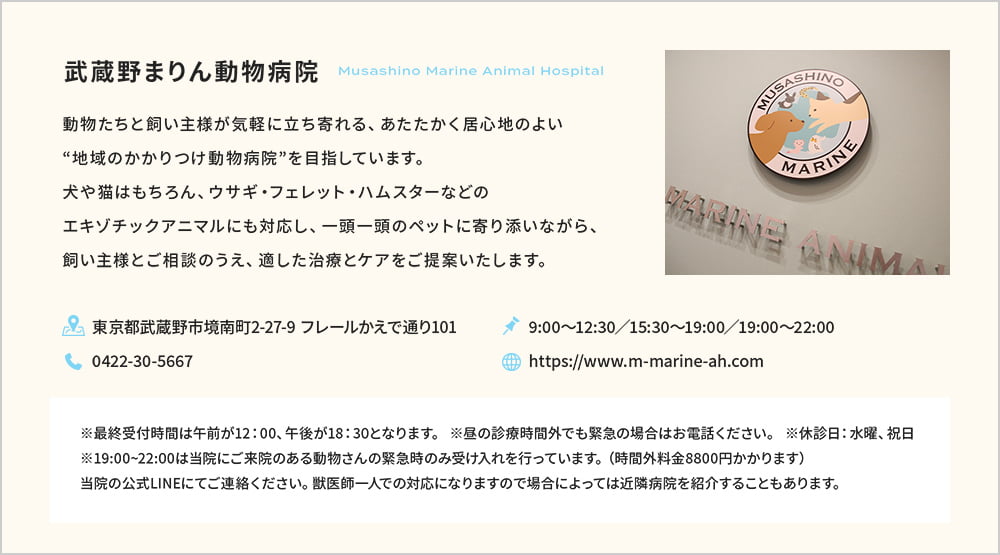【今話題】SFTSって知ってる?わんちゃん・猫ちゃんの飼い主さんに知ってほしい感染症の話
【今話題】SFTSって知ってる?わんちゃん・猫ちゃんの飼い主さんに知ってほしい感染症の話
目次
はじめに:最近ニュースでよく聞く「SFTS」ってなに?
最近、「SFTSで獣医師が亡くなった」というニュースを見た方もいるかもしれません。
「聞いたことはあるけど、何の病気?」「うちの犬・猫にも関係あるの?」
と不安に思う飼い主さんもいらっしゃると思います。
今回は SFTS(重症熱性血小板減少症候群)という感染症について、わかりやすくご紹介します。
動物に関わる病気ではありますが、実は人にも感染する可能性があるウイルスです。
特に犬や猫を飼っている方、これから飼おうと思っている方には、ぜひ知っておいてほしい内容です。
1.SFTSとはどんな病気?

SFTSはマダニが媒介するウイルス感染症で、正式名称は「重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)」といいます。
主に西日本で多く見られ、近年は毎年100人近くの患者が報告されています。
人が発症すると、発熱・嘔吐・下痢・意識障害・出血などの症状が出て、重症化すると命に関わることもあります。致死率は10〜30%とも言われており、決して軽く見てはいけない病気です。
2.感染経路は?どうやってうつるの?
SFTSのウイルスは、主に以下の経路で人や動物に感染します。
・マダニに咬まれる
野山や草むらなどにいるマダニに咬まれることでウイルスが体に入ります。ハイキングや畑仕事などで感染する人が多いです。
・感染した動物との接触
近年特に問題になっているのがこちらです。
感染した猫や犬の唾液・血液・排泄物に直接触れることで、人にも感染する可能性があることが分かっています。
実際に2025年5月、三重県の獣医師が SFTSに感染した猫を治療したあとに発症し、亡くなるという痛ましい事例が報告されました。
3.動物が感染するとどうなる?
SFTSは、特に猫での発症例が多く、症状も重くなる傾向があります。
感染した猫は次のような症状を示します。
・発熱
・食欲不振
・嘔吐・下痢
・元気がなくなる
・出血傾向や黄疸(目が黄色っぽくなる)
・意識がもうろうとする
発症後、数日で急激に悪化することもあり、致死率は60%を超えるという報告もあります。
犬でも感染例はありますが、症状が出ない(不顕性感染)ことも多いとされています。
4.SFTSの診断と治療
<診断>
SFTSは発熱や食欲不振の症状だけでは判断が難しいためいくつかの検査を行います。
〇血液検査
白血球数や貧血の有無、肝臓や腎臓の数値に異常がないかをチェックします。また、CRPやSAAといった炎症マーカーが上昇していることも診断のてがかりとなります。
〇PCR検査
よりSFTSが疑わしい場合にはPCR検査で血液中のSFTSウイルス遺伝子の有無を調べます。
他にも、x-ray検査やエコー検査を用いて全身状態の把握をします。
<治療方法>
残念ながら現在はSFTSの特効薬が存在しません。そのため治療は入院管理での点滴治療や吐き気止め、胃腸薬などでの対症療法が中心に行われます。
5.SFTS予防のために飼い主さんが出来ること
・室内飼育を徹底しましょう
猫を自由に外に出していると、マダニが寄生するリスクが高まります。
特に夏から秋にかけてはマダニが活発なので完全室内飼育が理想です。
・マダニ予防薬を使用しましょう
動物病院で処方されるマダニ予防薬(スポットタイプや飲み薬)を使うことが重要です。
・体調不良時はすぐ病院へ
猫ちゃんが急に元気がなくなった、熱っぽい、嘔吐や下痢が続くなどの症状がある場合は、早めに動物病院を受診してください。
もし、猫ちゃんが外に出た経歴がある、または最近マダニを見つけた、という場合は獣医師にその情報を伝えましょう。
・看病のときは防護を忘れずに
発熱している動物や、SFTSが疑われる症状がある場合は、素手で触れないようにしましょう。手袋やマスクをつけ、排泄物に触れないよう注意し、看病後は必ず手洗い・消毒を行ってください。
まとめ
SFTSは、マダニが媒介する感染症で、人にも犬・猫にも感染する病気です。近年では、猫から人への感染事例も報告されており、特に発症中の動物との接触には注意が必要です。
「怖い病気」と聞くと不安になるかもしれませんが、正しい知識と予防で多くの感染リスクは防げます。
実際、マダニ予防をしっかり行っている子や、完全室内飼育をしている子はSFTSの感染リスクは非常に低いとされています。
ペットちゃんと安心で安全に暮らすためにも、飼い主さんが「SFTS」について正しく知っておくことが、命を守ることにつながります。
わからないこと、不安なことがあれば、いつでもご相談くださいね。
以下のブログではノミ・マダニ予防について詳しく説明しています。合わせてご確認ください!
→【必読】ノミ・マダニ予防はなぜ必要?愛犬・愛猫を守るために知っておきたいこと
武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の
犬・猫・エキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」